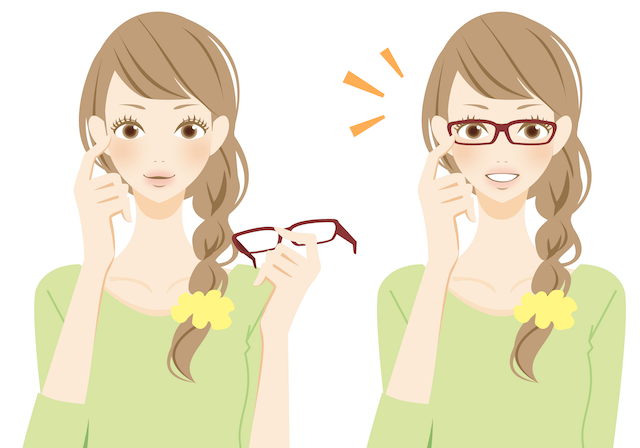「ウチの社長、存在感がないんです。いるのかいないのかわからないし…。ハッキリしないし…。社長らしく、強いリーダーシップをもって話してほしいのですが…」
広報担当者さんから、こんなご相談がありました。
「サラリーマン金太郎」のように強烈なカリスマタイプのリーダーならば、確かに強いリーダーシップを発揮します。外資系企業トップにはそんな方が多いですよね。しかし、リーダーシップは、それだけではないのです。
2018年1月24日、セールス・オンデマンド株式会社の「窓掃除ロボット 新製品発表会」で、室﨑 肇社長のプレゼンを取材してまいりました。
これほど自然体の社長はなかなか見たことがありません。身振り手振りもなく、まっすぐに脱力した立ち姿。それで淡々と語ります。まったくインパクトがないのです。
しかし「凄い」と思ったことがありました。
一切資料を見ず、すべて自分の言葉で語っているのです。当たり前のように思えますが、世の中では原稿がないと話せないトップはとても多いのが現実。商品に関するテクニカルな言葉も、完全に自分の中で消化して話しているのが伝わってきます。
実は室﨑社長は、一見地味な、本格派なのです。
そしてこの日、最も印象深かったことがありました。
小野寺英幸事業本部本部長が、エネルギッシュなプレゼンを行い大活躍。質疑応答でも社長を横にしてほとんどの質問に答えていました。室崎社長は、「俺を差し置いて」などとは微塵も感じさせず、むしろ自然体でそれを見ているのです。また、司会も社員が上手に担当、パートナーである韓国RF社のリ・スンボク社長も心のこもった見事な日本語で挨拶を行いました。
会場にいた社員とパートナー全員がイキイキと活躍する「全員会見」でした。
日本型と欧米型のリーダーの違いはエゴマネジメントなのかもしれません。強力なリーダーシップで組織を統轄する欧米型リーダーは、「自分はこういう考えだ」という強い自我(=エゴ)が求められます。しかしエゴが強すぎると、部下の良さを殺してしまうこともあります。こうなると組織の力は引き出せません。
しかし、室﨑社長のようなリーダーは、そのような強い自我はあまり感じられません。そのかわり自分の存在感を消して社員の積極性を引き出す「引き立て力」を持っています。
反面、このようなリーダーシップは物足りなさも残ります。それは明確なビジョンが見えにくいこと。会社のビジョンはトップしか語れないことです。
引き立て力によりチームの力を引き出し、そのスタイルは残しつつ、明確なビジョンも語れるようになれば、更に会社は成長していくのではないか、と感じた会見でした。
■当コラムは、毎週メルマガでお届けしています。ご登録はこちらへ。
■Facebookページで「いいね」すると、さらに色々な情報がご覧になれます。