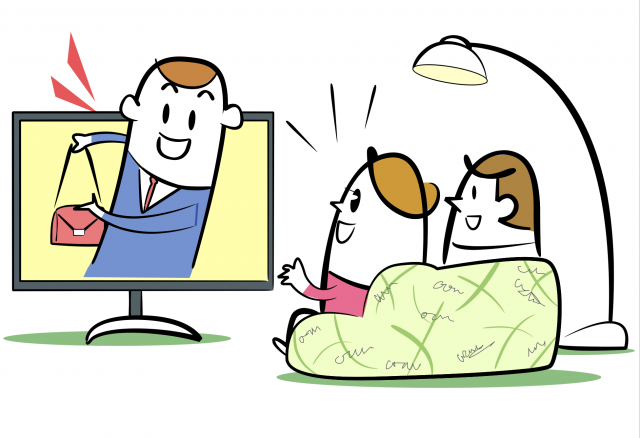こんなご相談をよくいただきます。
「声がか細くて聞き取り難いって言われます。響く声を出したいんです」
声が響くかどうかは母音で決まります。
子音はどんなに頑張っても響きにくいからです。
だから響く声に必要なのは、「あいうえお」だけです。
ただ、単に「あいうえお」を練習すればいいわけではありません。
そこで「響く声を出すための母音のトレーニング」についてお伝えします。
実は母音は、「アエイ系」と「アオウ系」の二系統にわかれます。
■まず「アエイ系」の発声方法です。
「ア」は、意識しなくとも響きやすいですよね。
でも「エ」と「イ」が響かない人が多いもの。
これは「エ」と「イ」を発音する時に、口の中が狭くなっているからです。
そこで「ア」の母音を基本にして、「エ」と「イ」が響く口の中のポジションをトレーニングすればよいのです。
実際に発音しながらやってみてください。
(1)基本は「ア」の口です。顎が下りてほおが十分のびている状態。舌はのびて舌先は下唇の上に触れています。
(2)「ア~」と発声しながら、舌の両脇を少しずつ持ち上げて、上奥歯に当たるところまで上げていきます。徐々に「エ」に変化していきますよね。「エ」と聴こえたら、そこで舌の動きを止めてください。このときの「エ」が、響く「エ」の母音です。
(一つだけ注意。舌と一緒に下顎が上がらないこと。上がるのは舌だけですよ)
ここでのポイントは「ア」から「エ」に移行する間を意識すること。
徐々に動きながら「エ」の響きに到達することです。このときの筋肉の動きがとても大事です。
例えば、手のひらを開いた状態からモノを握るとき、「パー」がいきなり「グー」にはらなずに、ゆるく握っている段階もありますよね。ちょうど卵を割れないようにやわらかく持つという感覚です。
舌を上げていく途中で「ア」と「エ」の中間のような曖昧な母音が聴こえてくるはずです。よーく自分の声を聞いて、音を確認しながらやってみて下さい。
(3)次は「イ」です。「エ」が出来れば、「イ」は簡単にできます。
先ほどの「エ」のポジションで「エ〜」と長く伸ばして発声をしながら、今度は少しずつ下あごを上げいきます。上げていく途中で「イ」と聴こえたら止めます。舌が奥歯に挟まれる感じが強くなります。そこが、響く「イ」のポジションです。
響く「イ」の声を、試しに離れた場所にいる人に聞いてもらってください。離れていても聴こえるはずです。
この「アエイ」系は、口の中を出来るだけ解放しながら、舌だけを少しずつ調節することで、響く声を獲得する方法です。
■次は「アオウ系」です。
試しに鏡の前で、普通に「アーオーウー」と一つずつ伸ばしながら発音してみてください。
唇がだんだんすぼまってきて、口の中がせまくなってきますね。
ただここで、「ウ」の時に口を噛み合わせて発音していると、響きません。
コンサートホールや教会では、空間の天井が高いほど、音は豊かに響きます。
実は口の中も同じ。口の中の空間が広いほど、響くのです。
逆に口の中の空間がないと響きません。
だから口の中の空間を確保することが必要になります。
では、やってみましょう。
(1)あくびをするときの口で「アー」と伸ばして発音したまま、口の中を変化させずに、少しずつ唇だけをすぼめていってください。鼻の下やあごの皮膚を伸ばすような動きです。
(2)唇の開きが500円玉くらいになると、自然に「オ」の音が聞こえてきます。「オ」と聞こえたら唇の動きをストップしてください。ここが響く「オ」のポジションです。
(3)そして、さらにすぼめていき、親指をしゃぶる程度の開きになったところで「ウ」が聞こえてくるはずです。ここが響く「ウ」のポジションです。
上手な人は、口の中の容積を保ったまま、舌を軟口蓋(口内の上奥にある柔らかい部分)の方へ引き上げて発音されるので、通常の響かない「ウ」とは比較にならないほどの豊かな響きとなります。
「ウ」は倍音が少なく、響きが作りにくい母音でもあります。できる限り、「アオウ系」の口のポジションを探り、口の中を「オ」の母音に近いところで響かせるようにしましょう。
「アエイ系」と「アオウ系」をマスターして響く声を獲得すると、驚くほど言葉が伝わるようになります。
ぜひお試し下さい。
■当コラムは、毎週メルマガでお届けしています。ご登録はこちらへ。
■Facebookページで「いいね」すると、さらに色々な情報がご覧になれます。