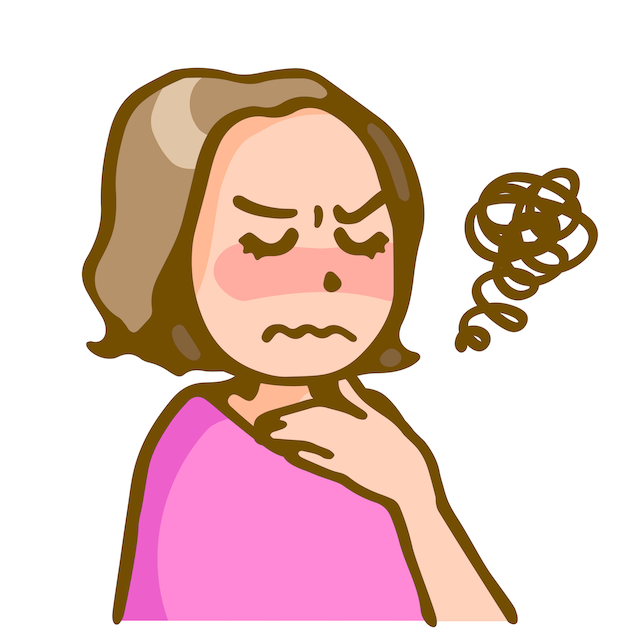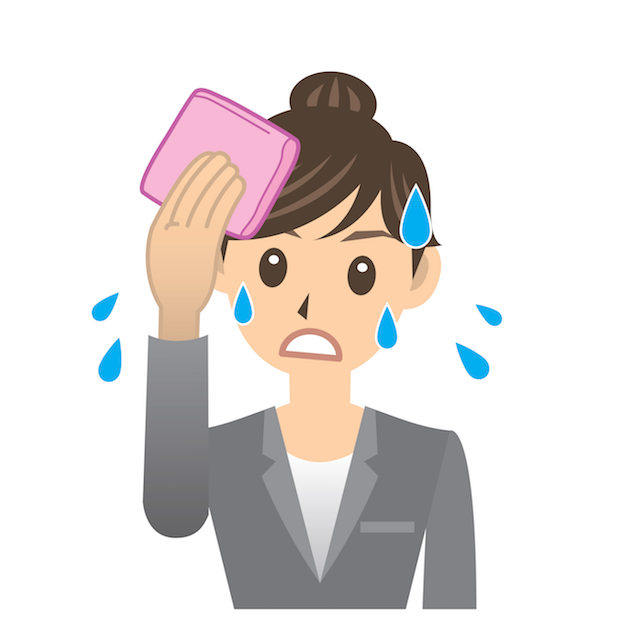「簡単なことをわざわざ難しく話してしまう」
という方が結構多くいらっしゃいます。
難しい話しをする方にはある傾向があります。プレゼンの後に質問をすると、その答えがさらに難しく、かえって分からなくなってしまうということが往々にしてあるのです。
「クロネコヤマトの宅急便」の生みの親である小倉昌男さんが、「『やさしく言えるから管理職』――できないのは自らが理解していないから」についてお話しされていたのがたいへん参考になります。
・・・・(以下引用)・・・・
・やさしく言えるから管理職です。聞く側(部下)が難しく感じるということは、理解できないということです。理解してもらわなければ、部下の方は会社が求めている行動が十分にできなくなってしまいます。
・人は理解していないことはやりたくないし、できないものです。部下を含めた社員がこれでは、組織はまとまりません。
・管理職の一番の仕事は、きちんと理解してもらえるように伝えることです。
・やさしく言えないというのは、管理職自らが理解していないということです。
・・・・(以上引用)・・・・
やさしく語ることは、相手の立場に立つということだと思います。
そのためには、まず自分ができる限り深く理解をして、そして、相手の立場に立って「もし自分が初めてこの話を聞くとしたら」という想像力を働かせなくてはなりません。プレゼンテーションは、自分が管理職でなくてもお客さんに理解して行動してもらうためのものですから、考え方としては管理職と同じです。
難しいことをやさしく説明するということは、内容を深く分かっていないとできないことです。子供向けの科学の本や辞典とか、初心者向けのビジネス書など、簡単に面白く書かれている良く出来たものの著者をみると、実は難しいところまで深く理解できている人が書いているのです。
やさしい言葉で語ること、つまり「自分が消化できている自分の言葉で語る」ことの大切さを感じています