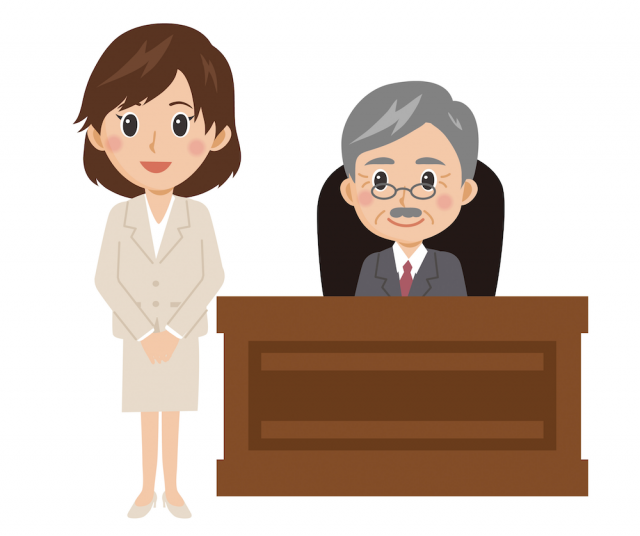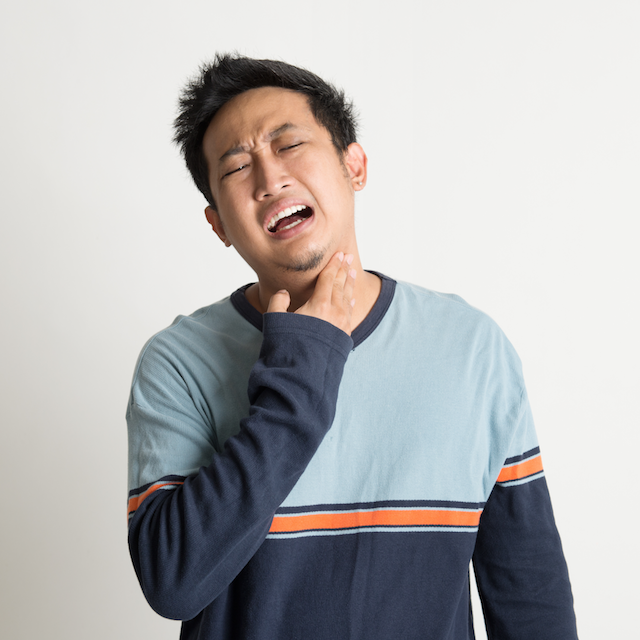
先日、ある企業のトッププレゼンを見てきたときのことです。最初は元気よく話していたのですが、開始後たった10分で声がかれていました。
声がかれてしまうと、本人もしゃべりにくいですし、声が通らなくなって内容が聞き取りにくくなってしまいます。
プレゼンで内容が聞きにくいのは困りものです。この問題は多くの方々に共通していて、「プレゼンで声がかすれないようにするためにはどうしたらいいのでしょうか?」という質問もよくうけます。
声がかすれる原因の一つに、緊張や空気の乾燥などでのどが渇いているということがあげられます。
このようなときは、応急処置として水を飲むと良いでしょう。プレゼンのときは、忘れずに水を用意しておきます。ただ、これはあくまで応急処置であって、水を飲んだとしても声の出し方が良くないと、またすぐに声はかれてしまいます。
声がかすれる主な原因は、声帯に無理なストレスがかかりすぎてしまった場合です。
「頑張って声を出すのだから、のどを使うのは当たり前」と思いがちなのですが、じつはのどに頼りすぎているせいで、声帯疲労を起こしてしまい、声がかれてしまいます。これは、一概に「大きな声を出しているから」ということではありません。声は、出し方を間違えると、ボリュームに関係なく小さな声でも声がかれてしまいます。
とくに、「今日は声が出ている」と手ごたえを感じるときこそ、注意が必要です。そういうとき、聴こえているのは自分だけで、あまり響いていません。つまり「近くはうるさく、遠くは聞こえにくい」という状態になっています。
のどにストレスをかけずに声を響かせることが大事なのです。
そのためには、二つの方法があります。
一つ目は、響きを作ることです。
「響きを作る」というと難しそうに聞こえますが、じつは皆さんが普段何気なくやっていることで響きは作られています。それは「ハミング」です。機嫌のよいときに「フ~ン♪フ~ン♪」と自然に出てしまうハミングは、響きを作る上で最も簡単な方法です。ハミングをした後、大抵の人は声に透明感が出て響きやすくなっています。ハミングしたときの「ライト感覚」で話すことがコツです。
二つ目は、横隔膜でささえることです。
横隔膜でしっかりささえれば、自然に息が流れて声が響きやすくなります。横隔膜を使うには、まず息をしっかり吸うこと。そして、おへその下9㎝の場所にある丹田を張ることです。こうすることで、のどに力みがいかなくなり、ストレスなく声を響かせられるようになります。
■当コラムは、毎週メルマガでお届けしています。ご登録はこちらへ。