ブログ「次世代トッププレゼン」
ブログ一覧
一瞬で記憶される方法

「”難しくて分かりにくい”とよく言われる」
「話が長くなりがち。よく時間をオーバーしてしまう」
こんなお悩み、よく伺います。
実はこれ、そんなに悪いことではありません。
話が長くなるのは、伝えたい事や話したいことがたくさんある証拠。
「難しくて分かりにくい」のも、思いが強過ぎて、ついつい哲学的に語ってしまいがちだからです。
でも、話が長くて分かりにくいと、聴き手に伝わりませんよね。
このようなタイプの方は「メタファー」を使うことです。
メタファーとは「たとえ話」のこと。
「たとえば、こういうこと」というように、誰でも分かるような例で説明するのです。
パナソニック創業者・松下幸之助さんは、ご自身の経営を「ダム(式)経営」と名付けていました。
川の水を満々と貯めるダムは、雨が降らなくても水を供給できます。
つまり「ダム(式)経営」とは、万が一のためにキャッシュをダムの水のように蓄えておくことの大切さを表現しているのです。
でも「常に余裕を持って万が一のために使えるキャッシュを持っておく経営をしなければいけませんよ」というとちょっと分かりにくいですよね。
でも「ダムのように経営しましょう」と言えば、小学生でも一瞬でわかります。
ソフトバンクの孫正義さんも上手にメタファーを使って話します。
2022年8月に行われた決算説明会でも、2022年4〜6月期連結決算で過去最大の赤字を計上したことを「三方ケ原の戦い」で武田信玄に敗れた徳川家康が慢心の戒めに描かせたとされる「しかみ像」を見せながら、反省の弁を伝えていました。
メタファーは、複雑な話を一言で伝え、確実に記憶に残すための武器になります。
話が長くて難しくなりがちな人は、ぜひご自分なりのメタファーを考えてみることをおすすめします。
野田元総理の追悼演説が見事だった理由
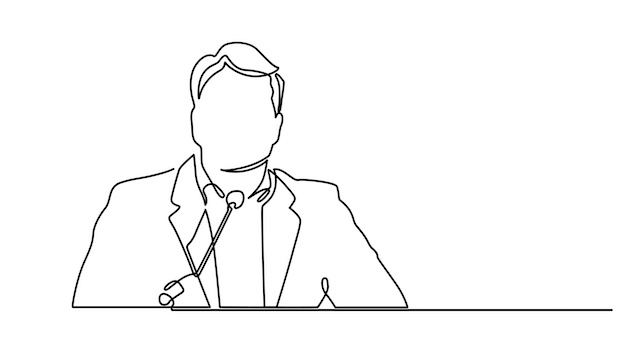
10月25日、国会にて立憲民主党の野田佳彦元首相が安倍元総理の追悼演説を行いました。
持ち前の低く響く重量感のある声を活かした見事な演説でした。
しかしこの演説で素晴らしいのは、話術ではありません。
考え抜かれた明確な「バリューポロポジション」があったことです。
バリュープロポジションとは
・お客様が求めていて、
・他の人が提供できないけど、
・自分だけが提供できる価値のこと。
自分が話したいことだけ話しても、聴き手が求めていないことならば、誰も聴いてくれません。
たとえ聴き手が求めていることでも、他の人でも語れる内容なら、聴き手は聞き流します。
しかし、その人しか語れない、聴き手が知りたいことならば、聴き手は必ず身を乗り出して聴いてくれます。
人前で話す場合、バリュープロポジションは、3つの質問で考えます。
〔三つの質問〕
1.聴き手が知りたいことは何か?
2.ライバルが語れることは何か?
3.自分しか語れないことは何か?
この演説では、野田氏は「安倍氏は『仇のような政敵』」と評したうえで、こんな話しを語りました
・安倍総理の親任式で、選挙で敗れた自分が前総理として同室になった控え室で、安倍氏の方から歩み寄り、重苦しい雰囲気を変えてくれた
・総理公邸の一室で密かに会ったとき、「(陛下の生前退位に向けた環境整備で)国論を二分することのないよう、立法府の総意を作るべきだ」と意見が一致し、立場の違いを乗り越え、政治家として国家のあるべき姿を論じ合えるのではないかと期待を持った
・遊説の際に「総理大臣たるには胆力が必要だ。途中でお腹が痛くなってはダメだ」と言ってしまった。謝罪が叶わなかった
どれも誰もが知り得ない、しかし聴き手が知りたかったこと。こんな話しを、野田氏はご自身の経験から存分に語っていました。
野田氏の演説は、見事にバリュープロポジションを組み立てていることがわかります。
〔野田佳彦氏のバリュープロポジション〕
1.聴き手が知りたいことは何か?:政敵・安倍氏との関係をいかに語るか?
2.ライバルが語れることは何か?:安倍氏の負の側面を語る(モリカケ問題など)
3.野田氏が語れることは何か?:野田氏の目線から見た仇敵・安倍氏との真剣勝負を語る
【バリュープロポジション】→安倍氏とのライバル関係を昇華し、最大のリスペクトで追悼する
この追悼演説は、野田氏がバリュープロポジションを明確にした上で語ったからこそ、演説終盤の「言葉と言葉、魂と魂をぶつけ合い、火花散るような真剣勝負を戦いたかった。勝ちっ放しはないでしょう、安倍さん。」という言葉に、ずっしりとした重みが宿ったのだと思います。
プレゼンが苦手な人が、一皮むける瞬間

ある新製品発表会でトップがプレゼンをしていたのを見たのですが、1年前と比較して別人のように上手になっていました。
もともと話すのは苦手な方でしたが「一皮むけた」と感じました。
そのトップに話をうかがいました。すると、
「いやぁ〜、この1年間で60回以上も人前で話しました。修羅場でしたよ」
と笑っています。
米国の有名なリーダーシップ研究機関、CCL(Center for Creative
Leadership)では、一皮むけるような仕事経験の特徴を「ハードシップ(修羅場経験)」と表現しています。
経営学者の金井嘉宏氏はこう述べています。
「一皮むけた経験をした人は、その経験を境にひと回り大きな人間、より自分らしいキャリアを磨く人間に変われる。ひと回り大きな人間になるとは、人としての器作りでもある。たとえば『社長の器だった』と言われるか『副社長止まりの器だった』と言われるかの分岐点にもなる」
修羅場が、人の器を一回りも二回りも大きくする。
だから名経営者と言われるような人ほど、修羅場の数が多いのですね。
これは、あらゆる人に共通です。一皮むけた経験は、人を脱皮させ、ひと回り大きな人間にしてくれます。
修羅場の最中は無我夢中で、とても辛いものです。でも、修羅場から逃げずに受け入れれば、人はより強靱に美しく変容することができるのです。
誰しも最初に人前で話すのは、あまり楽しいものではありません。
でもそれも受け入れて何度も話す機会を作ることで、一皮むけていくものなのです。
意外と誰もやらない、プレゼン結果を知る最も効果的な方法

プレゼンの後、悩んでいる方がいました。
「今回のプレゼン、絶対良くなかったと思うんです。つまらなそうに聞いている人も多かったし…」
せっかく面白いことを話しているのにウケが悪いと、こう思いたくなってしまうものです。
でも、他人の心の中は、意外とわからないものです。
ある絵画教室で、同じ「赤い」リンゴを描いていたのを見た時に、1人1人まったく違う配色だったことがあります。
人によっては青みがかっていたり、茶色だったり、黄色っぽかったり…。
私が赤く見えているリンゴが、他人も赤く見えているとは限らないようです。
さらに、絵の具のクオリティや、描き手の技術・体調も影響しますので、実際に描かれるリンゴが果たしてその人の頭の中にあるリンゴと本当に同じかどうかも分かりません。どう見えているか科学的に証明する手段もありません。このように、実際に置いてあるリンゴでさえ、人によって見え方が違います。
教育学者の田端健人氏は、「心理学的に他人の内面を知ることは疑問の余地があり、安易に他人の内面を判断することは危険」と警鐘を鳴らしています。
臨床心理学者で心理カウンセラーのロジャーズも、「他人の内面を知ることを確信しているわけではなく、出来るだけ内面を知ろうとする努力目標程度のものでしかない」と言っています。
専門的なトレーニングを積んだ心理カウンセラーでも他人の心は分からないのです。
つまり、いくら考えても、それだけでは人がどのように考えているかはわからないのです。
ではどうするか? 簡単な方法があります。それはアンケートをとること。
「なんだ、そんなことか」と思うかもしれませんが、実際には多くの方々はプレゼンの際にアンケートをとっていません。
冒頭で悩んでいた方もアンケートをとっていませんでした。
アンケートをとれば、聴き手の反応が分かり、余計な心配ごとも減ります。足りなかったところは次回に活かすこともできるのです。
プレゼンを控えている方は、ぜひ今度はアンケートを取ってみて下さい。
必ず何か発見があるはずです。
覚えて話せば、上手くなるし脳も鍛えられる

「ウチの社長、プレゼンのときはいつも台本を読み上げで困っています。
少しは覚えて自分の言葉で話してほしいんですけど」
広報の方からよく受けるご相談です。
しかし話す側のトップはこう思っています。
「最近、物覚えが悪くなって…。台本見ないと心配だからね」
「人は年齢を重ねると脳の学ぶ力も衰える」と思い込んでいる方が多くおられます。
そのため「もう年だから、ムリ」と考える傾向にあります。
実はこれ、都市伝説です。
脳科学的な見解から述べると、脳に年齢の限界はありません。
ニューヨーク大学医学部神経学臨床教授のE・ゴールドバーグや認知心理学博士のP・マイケロンらは「脳は鍛え続けることができる」と言っています。
専門的な話しをすると、人間の脳は、約1000億個のニューロン(神経細胞)があります。このニューロンの数は変わりません。
しかし脳は、これらニューロンがお互いにネットワークを作ることで機能します。
どのようにネットワークを作るかというと、これらニューロン同士を繋げるシナプスという連結部分を通じて、情報がニューロンからニューロンに伝わります。
頭を使うと、ニューロン同士のつながりが強化されて、ニューロンのネットワークが繋がるわけですね。
このニューロン・ネットワークに繰り返し刺激を与えれば、脳機能は鍛えることができるのです。
たとえば、新たに英語の学習を始めた人は、ニューロン・ネットワークのつながりが強くなり脳が鍛えられます。
でも英語が上手になって楽に話せるようになるとニューロン活動は低下します。この場合は、さらに難しい言葉を話せるようにチャレンジの度合いを上げれば脳は鍛えられるのです。
脳は無限の可能性があるわけです。むしろ「年だから、もうダメ」という諦めに縛られることで、脳の衰えと学ぶ力が低下します。脳は鍛えていなければ衰えていくということですね。
ですから、プレゼンを控えている方は、次回は内容を覚えてお話されてみてはいかがでしょうか。
脳が鍛えられますし、更にプレゼンも上達することができますよ。