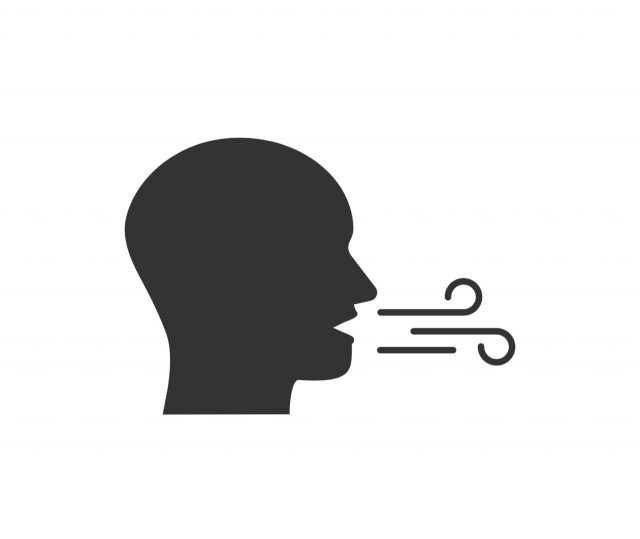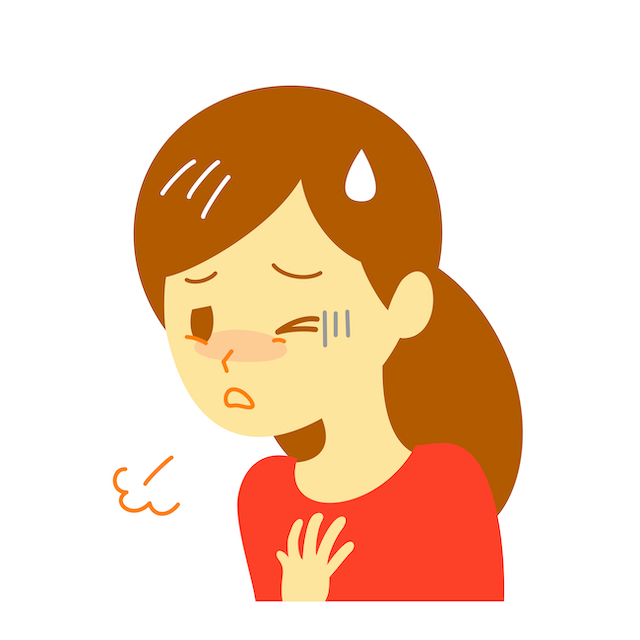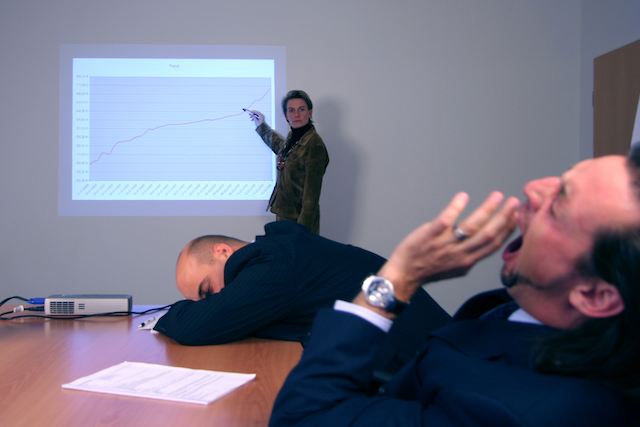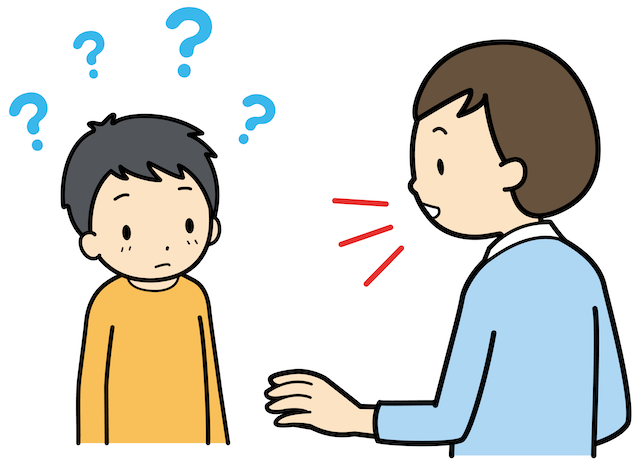声が小さい。声が通らない。響かない。だから聞き取り難い。結局、聞いてもらえないので伝わらない。
多くの方々にとって共通の悩みでもあります。
大きな声を出そうと思ったら「口を大きくハキハキとあけなさい」と良く言われています。
これは決して間違っていませんが、あまり口を開けずぎると響きが散ってしまい、かえって声が通らなくなってしまいます。
それに口をパクパクして話すのは、ビジネスのシーンやフォーマルな場でエレガントではありませんね。
声を響かせるためには、口の前を開けずに「口の中」が開いていることが大事です。特に縦方向に開いていることがポイントです。
良く響く教会やホールは天上が高いですよね。口の中も同じです。逆に野外ホールはオープンになっていますが声は響き難いものです。プロのオペラ歌手でも野外ホールで演奏するときはマイクを使わなければ声は届きません。
一方で現代人は、アゴの骨格が小さい傾向にあり、口の中が狭い方が多く、大きく縦に口を開けることが難しいのも事実。その結果、声がぺちゃっとして響かず、舌足らずのような話し方になってしまいます。
対策があります。口はあまり開けず「おちょぼ口」にし、アゴを下げることです。見た目は「ハコフグ」のようになります。
口の中を開け、声を響かせるためのトレーニング方法をお伝えします。
(1)口を閉じる。舌を下げて舌先が下歯茎に触れている状態を維持
(2)唇を少し開けて、アゴを下げる。下げるときのコツは下アゴを前に少しだけ出す感じで「受け口」気味に。
(1)と(2)を10回程繰り返し、アゴ周辺の筋肉をほぐし、アゴの可動域を広げる。
慣れてきたら、声を出してみましょう。
(1)口を閉じる。舌を下げて舌先が下歯茎に触れている状態を維持
(2)唇を少し開けて、アゴを下げ、「Mo〜〜」と長く伸ばして発声する。発声しているときは下アゴを少しだけ前に出し、舌は舌歯茎に触れている状態を維持。
見た目は「ハコフグ」です。鏡で確認してみてください。
ドイツの名歌手に、シュヴァルツコップ(Olga Maria Elisabeth Frederike Schwarzkopf,1915-2006)という人がいます。彼女は小柄だったので、ヨーロッパの大柄な歌手たちと声量の差をうめるために口周辺の作り方を細かく工夫していました。口の開け方は、アゴを下げることと、アヒルっぽく上唇をほんの少し前に突き出すことも行っていました。そうすることで、声がより前に響くようになるからです。この方法は、同じように、骨格の小さい日本人のお弟子さんたちにも彼女は勧めていたそうです。口の作り方をちょっと変えるだけでも、響きが劇的に変わります。
職人は、その職業に合わせて体を作りかえると言います。
声もビジネスにおいての道具になります。
ビジネスでも声という道具を使いこなすために体を作っていくことも大事なことだと思っています。