ブログ「次世代トッププレゼン」
ブログ一覧
怖い質問が楽になる便利な言葉

「質問が怖い」。皆さん、よくおっしゃいます。
緊張して臨んだプレゼンで、厳しい質問をされるのではと思うと、余計に緊張してしまいそうです。
それに、「なぜこんなことを聞いてくるんだろう、何か意図があるのでは?」と思わずムッとしてしまいたくなることもあるものです。
憂鬱になりそうな質疑応答ですが、これさえ覚えておけば楽になります。
『すぐに答えなくていい』。
もし困ってすぐ答えられなかったら、少々黙ってもいいですし、答えたくなければ真っ正直に答えなくてもいいのです。
間違っても「あ〜」とか「え〜」とか言って、沈黙を自ら打ち破ってはいけません。緊張しながら「それで、え〜、だから、あ〜」などと行っていると、相手に「困っているな」とすぐに分かってしまいます。
瞬発力は必要ありません。
良い答えが浮かぶまで時間をとりましょう。
そのために便利な言葉があります。
「良いご質問ですね…」
「面白いご質問ですね…」
加えて、斜め上を見上げ、言葉が降りてくるのを待つポーズをとると効果的です。
質問者や会場の方々も「真摯に答えようとしているな」と安心します。
ムッとしたときも、時間をとれば感情を爆発させずクールダウンさせることもできます。
ちょっとした時間で良い答えが浮かぶものです。
皆さんは、本当はベストの答えを知っているのです。ただ、ちょっと慌ててしまったり、動揺してしまって良い答えができないだけなのです。
厳しい質問には、「瞬発力は百害あって一利なし」と割り切って、ぜひ時間をとってみてください。
リーダーの涙は隠さなくていい。でも嘘泣きは厳禁
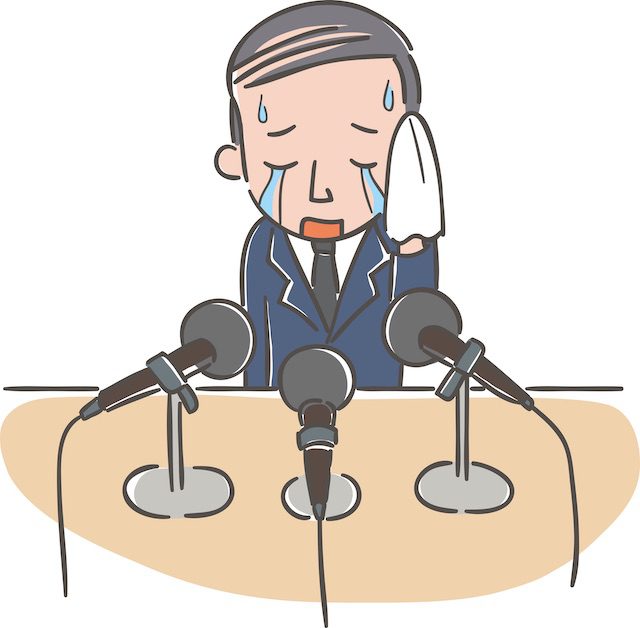
運転免許停止中に人身事故を起こし書類送検され、7回にわたって無免許運転をしたとして在宅起訴された木下富美子都議の会見が話題になっています。
会見が火に油を注ぎ、SNSでも「反省してない」「不快」とネガティブな感想が多く見られました。
これで思い出されるのが、2014年、詐欺罪で有罪となった野々村元議員の号泣会見。こちらも大きく炎上していましたね。
脳科学的な知見によれば、人間の脳は、無意識の世界で他者のわずかな感情や行動の表現を読み取る「共鳴」という仕組みを持っています。作り笑いや嘘泣きを見ると無意識に不快に感じるのもこの仕組みのため。だからムリに演じて見せても、聴き手はどこか違和感を感じてしまうのです。
ハーバード・ビジネススクール教授のビル・ジョージが2003年に提唱した「オーセンティック・リーダーシップ」が注目されています。オーセンティックとは「本心に偽りがない」という意味です。
ウソ偽りのないリーダーに対して人は絆を感じるようになります。人間的な絆を感じながらの仕事は、高いお給料よりも社員の忠誠心を高めることも分かっています。
たとえば、トヨタの豊田章男社長は、リコール問題で米国公聴会の謝罪後、従業員の前で激励の声をかけられ涙ぐんでいました。これはトヨタ社員の結束を高めました。
1997年11月24日、倒産した山一證券・野澤正平社長の会見。「社員は悪くありませんから。どうか社員の皆さんを応援してやってください」と号泣しながらの謝罪会見を行いました。その後も、野澤社長を慕う社員はとても多いのです。
「経営者たるもの、人前で泣くなんて言語道断」と思われるかもしれませんが、真実なら感情を隠さなくても良いのです。だから泣くのもあり。でも本心を偽った嘘泣きは厳禁です。
ここ一番のプレゼンや会見でも、聴き手の心を動かすのは「自分らしさ」。
自分自身を見つめ、自分らしさを貫くことがリーダーに求められているのです。
プレゼンで人を突き動かす方法

「話し下手だからスルーされちゃって伝わらないんですよね…」というお悩みを多く聞きます。
実はスルーされるのは最悪です。プレゼンの目的は、聴き手に何かを伝え、良い方向に行動を変えてもらうこと。この目的が達成できないからです。
しかし、話し下手でもスルーされない方法があります。
それは「誰もが共感する大義名分」から話し始めること。
つまり「Why」から話すべきなのです。
人は、「それをする意義は何か?」というWhy=大義名分や理念に共感します。
しかし現実には、ほとんどの人は「What」(製品・プロジェクト)や「How」(使い方・方法)しか語りません。
だからスルーされてしまうのです。
人々の心を突き動かす人たちは、必ずWhyを話しています。
低迷するソニーを復活させた前CEOの平井一夫さんは、「ソニーは方向性を失ってしまっている」と感じていました。
そこで「ソニーは『感動』を提供するために存在する。それが今のソニーが目指すべき姿だ」と考え、新しい時代のソニーが向かうべき方向性を示す言葉を「KANDO」(感動)という一言で言い表しました。
この「KANDO」こそが「ソニーはどのような大義や使命のために存在しているのか?」を語るWhyなのです。
平井さんは、世界中の拠点を回り、70回以上のタウンホールミーティングを行い、社員たちに「KANDO」を語りかけてきたと著書「ソニー再生」で述べています。
しかしWhyが語られていなければ、いくら話し方が上手でも人の行動は変わりません。
「プレゼンがスルーされてしまう」とお悩みの方は、一度プレゼン資料を見直してみましょう。
あなたはWhyから語っていますか?
【参考文献】
サイモン・シネック『Whyから始めよ!』日本経済新聞出版社(2012年)
平井一夫『ソニー再生』日本経済新聞出版(2021年)
プレゼンで聴き手の反応が良くなる方法

「内容も良くて、プレゼンも上手くいったはずなのに、なぜかお客さんの反応がいまひとつ良くないんです」
このようなお悩み、本当によく伺います。
一言でいうと、「ウケが悪い」ということですね。
内容の良いことが大前提ですが、プレゼンで格段に聴き手の反応を良くする方法があります。
それは、聴き手に問いかけることです。
聴き手は話しを聴きに来ているのに、なぜ問わなくてはいけないの?と不思議に思われるかもしれませんね。
じつは、聴き手に問いかけることで、相手を敬う気持ちが伝わります。人は、他人から敬われて無視することはできません。
また良い問いは、聴き手に刺激を与え、思考を促します。
退屈することがないので、反応も良くなるのです。
以前、KDDIの高橋誠社長の会見を取材したことがありました。高橋社長は記者の顔を良く覚えていて、囲み取材では頻繁に問いかけていました。
私は70回近くトップの会見取材を重ねていますが、ここまで記者の反応がよかったのは見たことがありません。
会見後も、メディアで多くの記事を見ることができました。
お客さんの反応が悪いと悩んでいる方の殆どは、自分が話すことに力を注ぎすぎています。
一度、自分が話すことから少し距離を置いて、聴き手に「考えを聞かせてほしい」と問いかけ、その話に耳を傾けてみてください。
一人、二人に問いかけるだけでも、全体の反応が良くなります。
「今日はなんだか反応よくないなあ」と感じたら、ぜひ、お試しください。
困った数字の質問に答える方法
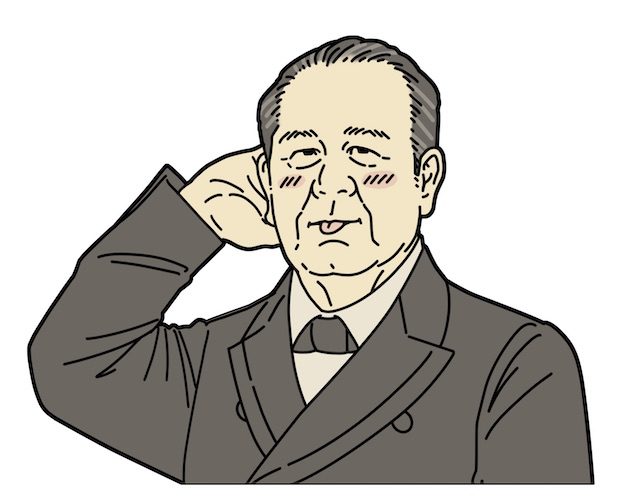
「ウチの社長、サービス精神旺盛で、メディアの前でつい数字を言っちゃうんですよね…」
広報担当者さんのよくあるお悩みです。
メディア対応で困るのが「数字」に関する質問です。
とくに記者会見で、販売目標数値などの質問の回答は注意が必要です。
短期的成果が求められがちな現代において、数字を言う場合は慎重に検討し、覚悟を決めて言うべきなのです。
ただ、何でもかんでも「お答えできません」では印象がよろしくありません。
そこで本日は、質疑応答で困った数字の質問を受けたときに、上手く乗り切る方法の一つをお伝えします。
2019年8月、三井不動産の「日本橋再生計画第3ステージ 記者発表会」にうかがったときのことです。
三井不動産は、首都高の高架橋を撤去し、日本橋に青空を甦らせる日本橋再生プロジェクトを進めていました。そのためには首都高速道路の地下化が不可欠なのですが、「(地下高速道路)わずか1キロで数千億円もかけるのはいかがなものか」と必要性を疑問視する声も一部ではあがっていました。
そのような社会的な背景もあったため、菰田社長が「非公開」と明言しているにも関わらず、記者から事業投資額に関する質問が繰り返されました。
緊迫感が高まり、ついに菰田社長は横に立つ広報担当者に「答えますよ」というような目線を送ると、「数千億から1兆円の間ってことでしょうね。ちょっと幅が広くて申し訳ないんですけど」と茶目っ気のある笑顔を向けたのです。
決定的な数字は言わず、許容範囲ギリギリのところで乗り切った絶妙な回答だったと思います。この「数千億から1兆円の間」は、後日メディアで多く露出していました。
非公開の数字を聞かれて答えるのが難しくても、ヒントをあげたいときがあります。
そのようなとき、「ちょっと幅が広くて申し訳ないんですけど」に、プラス「笑顔」。
困った数字を聞かれたときに、ぜひお試しください。