ブログ「次世代トッププレゼン」
ブログ一覧
一晩中泣く赤ちゃんが声枯れしないワケ

「声に自信がない」という方が多くおられます。
でも、本来、人は良い声を持っています。
赤ちゃんが生まれると「オギャー!」と良い声で泣いていますね。赤ちゃんはどんなに一晩中泣いていても声が嗄れることはありません。しゃがれ声の赤ちゃん、なんて聞いたことありません。どんな人でも、平等に良い声を持って生まれてきているのです。
しかし、人生経験を積み重ねる中で、どこかおかしな発声になってしまい、良い声が出せなくなってしまうのです。
例えば、子供の頃「こんな声を出してはいけません」と注意を受けたり、小学校で友達に「変な声」とからかわれたりします。そうすると、自分なりに「こんな声がいいかな?」「こんな風に出すと格好良いかな?」と、間違った方向に工夫し始めます。
そのような状態になると、赤ちゃんの頃は素直に合っていた声帯は、少しずれた方向に働いてしまいます。そして、人生を重ねれば重ねるほど、声帯がおかしな方向に働いてしまう癖がついてしまうのです。つまり、「声帯に厚着をしている」ようなものなのです。
一般的には、声を良くするために始めると思われているボイストレーニングですが、じつは、声帯の厚着を一枚一枚脱がしていって、本来持っていた良い声を取り戻すのが目的です。
ボイストレーニングでは、声帯の働きがずれていることに気がつき、方法を変えていくことが、無駄なく最速で上達するコツでもあります。
「トップとメディアのリレーションが作れない」というお悩み

先日、広報担当者さんからのご相談がありました。
「トップとメディアとのリレーションが上手く作れないんですよ」
メディアとのリレーション作りが上手いトップには、二つの特徴があります。
一つ目は、時間をかけること。
トップ就任後にあわててリレーション作りをしてもなかなか難しいものです。
ある通信系会社のトップは、トップ就任の部長時代から、じっくりと時間をかけてメディアと関係作りをしてきました。その結果、トップ就任直後にもかかわらず、会見後の囲みでは一歩も二歩も踏み込んだ深い内容の質問が多くでていました。
二つ目は、メディアからの質問には誠意を持って答えることです。
最近は些細なことでも「詳細は話せません」と紋切り型で答えるトップが多いように思います。もちろん話してはいけないことはいうべきではありません。しかし少しでもリスクがあれば「答えられない」と言い切っていては、メディアとの関係を作るのは難しいかもしれませんよね。
ある食品会社のトップは、普通なら回答NGの難しい質問を受けても、「話せるギリギリの範囲で、少しでも相手に満足いただきたい」と考え、ちょっとしたヒントを与えたりして回答しています。メディアへの真摯な姿勢と誠意を感じます。
メディアとのリレーションも人間の関係です。一朝一夕には出来るものではありません。時間をかけて、誠意をもって関係作りを行っていくことが良い方法だと思います。
「では、ひと言」といきなりいわれたら…

何かの集まりで、いきなりこうなることってありますよね。
「はい、それでは一言お願いします」
こんなとき(スッと話せたらいいなあ)と以前から思っていました。
昔はよくしどろもどろになり、話し終わって「要はなに?」という状態になっていました。
最近、人前で話すときに気をつけていることがあります。
話す前に、おおまかに話すことを考えて立つことです。
3分程度の短いものでも、必ず構成を考えます。
たとえば3部構成にして、
1部「自分の紹介」(名前だけか、肩書きを一言のみ。最短時間が好ましい)
2部「その場の方々に関連する話し」
3部「まとめ」
このように、簡単に頭でまとめてから話します。
こうしないとダラダラ話したり、「あー」とか「えー」とか言って考えながら話すことになり、人の時間を無駄に使ってしまいます。
「要はなに?」
話し終わったときにそうならないようにしたいですよね。
(気の利いた話をしよう)なんて思わなくても良いのです。
話の構成がまとまっているだけで、人に伝わる話しになります。
頭の中でまとまっていると、次に話すことが頭に思い浮かばずに頭が真っ白になることもありません。落ち着いて話せます。
落ちついて話せれば、あせって早口になり、つっかえることもなくなり、皆さんとアイコンタクトもとれます。
何より良いのは、しっかり息を吸い横隔膜が使えて良い声で話せるので、説得力のある話し方ができることです。
そろそろ忘年会の準備も始まる時期。
ぜひお試し下さい。
姿勢を直せば、声が改善する

プレゼンで声が良くない人に共通する点があります。
姿勢が良くないことです。
発声のときに姿勢が悪いと、なかなかボイストレーニングの効果は発揮されません。
普段、椅子に座っている時間が長い人は、肩が斜めになっていたり、アゴが出て猫背になっていたりなどの状態が多く見られます。
ほとんどの方はご自分の状態に気がついていいません。
壁に背中はりつけて発声することで、違和感のあるところに気づくことができます。
壁に背中をはりつけて立ちながら発声すると、首、頭、肩、背中、腰、あごなど、発声のボトルネックになっているところが分かります。そしてこの方法を継続することで少しずつ姿勢と発声を矯正することも可能です。
もう一つの方法は、「丹田」と言われる、へそ下9センチの場所を張って力をこめることです。
そ
うすると、どんな人でも自然に良い姿勢になることができます。「姿勢良くしましょう」と言われると、肩に力が入ってしまったり、背中が緊張してしまったり
して、姿勢が長続きしないものです。しかし丹田に力を込めると、良い姿勢を作ることが出来て、声も格段に良くなります。
最後に、もう一点気をつけていただきたいことがあります。
「肩が内側に入っていないか」というとです。
パソコンを使う人に多いのですが、肩が内側に入ってしまう姿勢です。一度、肩が内側に入る癖がついてしまうと、矯正が難しくなります。
これを一瞬で矯正する方法があります。
(1)両腕を斜め下にまっすぐ伸ばす
(2)手の親指側を上に向けて「クルッ」と軽く手のひらを後ろにかえす
そうすると肩と胸がすっきりのびて良い姿勢になります。気がついたときに頻繁に繰り返すことで、肩が内側に入る癖を直していくことができます。
プレゼンに夢中になるとつい忘れがちですが、気をつけたいところですね。
力んで声がかすれる人へのアドバイス
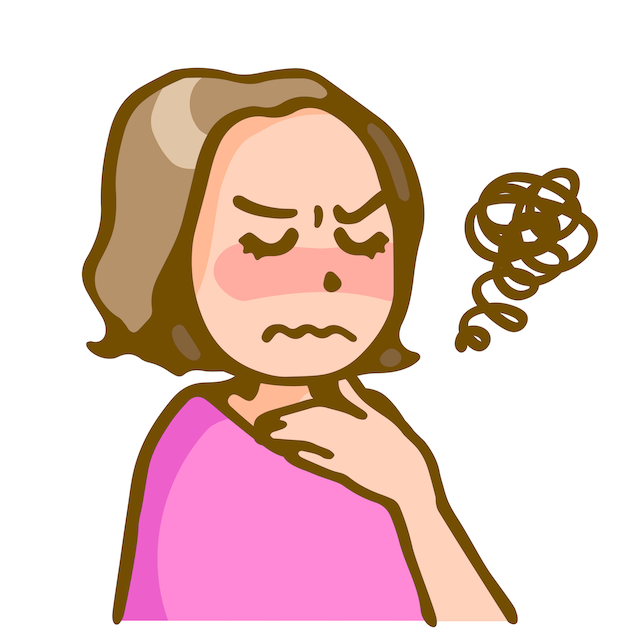
「ついつい力んで話してしまい、声がかすれるんです」
こんな相談を受けることがよくあります。プレゼンの後や会議の後に、声がかすれてしまったり、喉の疲労がたまってしまう方が多いようです。
「伝えたい」という気持ちが強く、一途であったり、一生懸命であったりする傾向にある方々に多くみられます。
だから、「つい力んで、身が入ってしまう」ということは、冷めていたり、感受性が弱かったりする人よりは何百倍も可能性があり、必ずしも悪いことではありません。
ただ、声力みは声帯に余分なストレスがかかってしまい、声嗄れの原因になってしまいます。話す量も多い政治家においては、ガラガラ声の方が多いのもその理由です。すぐ休めば良いのですが、継続しすぎると声が戻らなくなってしまいますので注意が必要です。
ついつい声が力んでしまう方向けの練習方法があります。
ガラス磨きをするときや眼鏡を拭くときに「は〜」と息を吹きかけ、磨くことがありますね。
その息でそのまま発声するのです。
【ガラス磨きボイトレ】
窓やメガネを「は〜」と磨きながら何かしゃべり、またすぐに「は〜」と磨いてしゃべり…を繰り返します。(プレゼンの練習をしながらやれば、窓やメガネも綺麗になり、プレゼンも上手になって一石二鳥です)
コツは、「は〜」の息のまま発声することです。最初はふわっとした感じの声になります。
少しずつ、力みがとれて、楽な発声に変わっていきます。
【フクロウボイトレ】
もう一つの方法は「フクロウ」の発声法です。
フクロウが「ホー」と鳴くときの真似をします。これ、意外にコツがいります。
「ホ〜♪」と、感情を込めてやろうとしてはダメです。
一生懸命な人ほど、フクロウの鳴き声にまで感情がこもってしまいます。
あくまで、本物のフクロウが、何も考えずにただ鳴いているように、「ホー」と鳴きます。
それが出来るようになったら、その「ホー」を、ロングトーンで「ホーーーーーーー」と伸ばしていきます。
最初は大きな声が出ないので、欲求不満になってしまうかもしれませんが、発声して「はあ〜、スッキリした!」というのは大抵喉に負担がかかっていますので方向性がずれています。発声に「手応え」を求めてはいけないということです。声帯に負荷がかかっていなければ、意外と声は響いていますので安心してください。
ぜひ、プレゼン前にお試しください。