ブログ「次世代トッププレゼン」
ブログ一覧
プレゼン舞台に歩いて出るための、3つのコツ

プレゼンの舞台に出てくる様子は意外に目立つものです。
なぜなら聴き手は「どんな話しになるのだろうか」「この人はどんな人なのだろうか」と、集中して見ているからです。
聴き手の集中力は、あくまで感覚的なものですが、
1分…100%、3分…80%、5分…50%、10分…35%、20分…25%と下がっていきます。
だから、舞台に現れる冒頭というのは、最も聴き手の集中力が高い時間帯なのです。
その大事な冒頭で、落ち着きなく出てきたり、猫背でやる気が感じられなかったり、変に虚勢を張りすぎていたりすると、聴き手に与える印象が悪くなり、聞いてもらえません。もちろん耳では聞いていると思いますが、心から聞いてみようという気持ちが下がってしまうのです。
ちょうどよい加減で歩いてでるには、コツがあります。
(1)心拍数と同じ速さで歩く
歩く速度が決められず、ノソノソ歩いてしまったり、逆に早足すぎたりすることがよくあります。直前に自分の心拍数を測ってその速さに合わせてでると丁度良い歩調で出られます。心拍数が遅い人も、はやい人も、その人らしく出られます。
(2)人混みを歩くときの感覚
意識し過ぎて不自然になってしまうケースです。硬くなってしまい左足と左手が同時に動いたりするケースも見られます。この原因は、自分に意識が向きすぎているためです。
こういうときは、駅の人混みを歩くときの感覚を思い出すとうまく行きます。
人混みでは向こうから歩いてくる人を避けながら歩きますよね。そのときは意識が前から歩いてくる人に向きます。
普段、駅を歩くときに、プレゼンのときはこう歩こうと考えながら試すと、本番でも自然に歩けるようになります。
(3)「どう話そうかな」と考えながら出る
ちょっと上級者向き。歩くことを意識するのではなく、話すことが決まっていたとしても「どうやって話そうかな」と思索しながら出る。もちろん「話す事はバッチリ決まっている」のが大前提です。これが出来ると、自然で、かつプレゼン慣れして見えます。
今日は、3つのコツをお伝えしました。
ぜひ普段から「今度のプレゼンはどうやって出ようかな」と考えながら行動してみてください。
「え」と「い」を変えれば、あなたの声は響く

「声が響かない」「声が良くない」
というお悩みを持つ方に共通するポイントがあります。
「え」と「い」の母音が響いていないことです。
ほとんどの人は、「え」と「い」を発音するとき口の中の空間が狭くなっています。こうなると音声の質が平べったく変化して聴き苦しくなり、加えて響きが浅くたるため幼稚っぽい声になりやすく、説得力も落ちてしまいます。
「え」と「い」が響かせることができれば、説得力が上がります。
さらに「え」と「い」を響かすことができれば、他の母音「あ」「う」「お」も響すことも簡単です。
そこで本日は、「え」と「い」を響かせる発声練習をお伝えしたいと思います。
■「え」の発声
1.基本は「あ」と発声する口の形。顎が下りてほおが十分のびている状態です。舌はのびて、舌先が下唇の上にさわっています。
2.「あ~」と発声しながら、舌を少しずつ持ち上げます。そうるすとだんだんと「え」に変化していきます。途中「え」と 聴こえたら舌の動きを止めてください。そのとき注意しなければならないのは、下あごが舌と一緒に上がってこないこと。上がるのは舌だけです。
「え」を響かすことが出来れば、「い」も簡単にできます。
■「い」の発音
1.先の「え〜〜」の発声をしながら、下あごを少し上げていきます。途中で「い」と聴こえたらあごを上げるのを止めてください。舌の両脇が奥歯に挟まれる感じになります。
この発声法が上手くいくと、声がマイクで話しているように離れたところで響いて聴こえます。
ぜひお試しください。
プレゼンが素晴らしく見える最後の決め手

プレゼンが素晴らしい女性は誰ですか?」
女性から、こういう質問を受けることがあります。
もし一人挙げるとすれば、それはIMF専務理事・クリスティーヌ・ラガルドさんです。
(※2019年7月3日加筆:このコラムを書いた翌日2019年7月2日、ラガルドさんは欧州中央銀行(ECB)総裁に就任しています)
ラガルドさんの男性に媚びることがなく、だからといって女性らしさを失わないふるまいは、社会で活動していこうとする女性の良いお手本となる存在です。
凄いのは、低い声で、しっかりと迷い無く言葉を発するところ。ラガルドさんご自身が、腹の底から信じているので言葉に力が宿り、聴き手の不安が消え、「大丈夫だ、出来る」と思えてきます。
ただ、言葉だけではありません。
まず、ファッションセンスも見事です。黒やグレーのスーツでも色味のあるスカーフをあしらい、顔周りを華やかに演出をしています。さりげなくフランスのブランド、ルイ・ヴィトンやエルメスのバーキンを持っているのを見ると、こういう方こそふさわしいと思ってしまいます。
加えて、姿勢が良いのも、素敵に見えるポイントです。ラガルドさんは、1971年にシンクロナイズドスイミングのフランス選手権で二位を獲得した経歴の持ち主です。だから姿勢が良いのでしょう。
そして大きな強みになるのは、シンクロを高い領域まで究めた経験ではないでしょうか?これが彼女に黙っていても伝わる品格や教養を与えています。
高い技術を持つピアニストである米国の政治家、コンドリーザ・ライスさんも同様でしょう。
「日経ビジネス」2014.12.29 No.1772「遺言」にて元首相の細川護煕さんがが興味深いことをおっしゃっていましたのでご紹介します。
・・・・(以下、引用)・・・・
教養は数値でははかれませんが、重要なものです。トルーマンは原爆投下時の米大統領ですが、英国のチャーチルは当初、彼を軽蔑していて敬称に「ミスター」を使っていた。それがある晩餐会後にトルーマンは得意なピアノを披露し、それ以降「プレジデント」に変えたそうです。
トルーマンはピアニストを目指すほどの腕前。チャーチルもそれを解して、敬意を示したんですね。
ピアノでも本でも何だっていい。にじみ出る教養は人を引き付けます。日本では政治家も経営者もハウツーものばかり読んで、そこが不得意ですね。でもこれからはそういう人が
必要でしょう。
・・・・(以上、引用)・・・・
教養とは、長い経験と年月を経て蓄積され、内側からにじみ出るもの。それがプレゼンでは最後の決め手となるのです。
プレゼンで集中力を高める方法
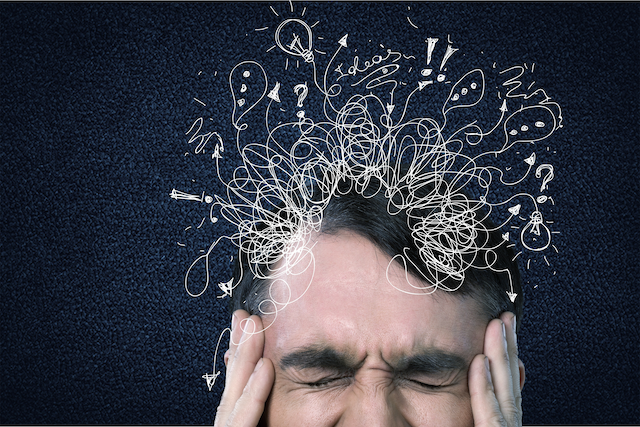
こんなご相談を受けることがあります。
「集中力がないんです。プレゼン本番でいろいろなことが気になってしまって…」
プレゼン本番で緊張すると、周囲の雑多なことが気になり、なかなか1つのことを考えにくくなるものです。これは、緊張すると誰でも起こります。決して、集中力がないわけではありません。
しかし緊張していても状態でも、集中力を高めてプレゼンを成功させたいもの。
じつは緊張していても実力を発揮しやすくする方法があります。
それは「オノマトペ」という方法です。
オノマトペとは擬音で、物事が動く様子を、「だーん!」とか「ぽん!」とかで表現する方法です。
たとえば、けん玉で玉を一回転させていれる「飛行機」という技は、「ジッ、ブラーン」というオノマトペで行うと成功しやすくなります。
スポーツでも応用できます。
ゴルフのスイングでも声を出さなかったときと出したときでは飛距離が違うそうです。
オノマトペは、集中力を高めるだけではありません。商品をオノマトペを使って表現することで、より聞き手の期待値が高まり、商品の価値が伝わりやすくなっていたのです。
あのスティーブ・ジョブズも、デモの最中に「ブン」と言うなど、オノマトペを巧みに使って表現していました。
なかなか集中できず、失敗しやすい方は、ただ機能説明をするだけではなく、自分なりのオノマトペを使って表現してみることをお試し下さい。
環境がプレゼンの満足度を落とす理由

「会場が寒かった」「会場が暑苦しかった」
こんなコメントを聞くことがあります。
実は、プレゼン会場の環境は、満足度にダイレクトに関係します。
今日は、プレゼンでお客様をお招きするときの、環境についてお伝えいたします。
プレゼンは、聴き手の「知覚」でも判断されます。
知覚とは、人の主観的な判断によるものです。
つまり、寒すぎたり、暑すぎたりと環境が良くないと判断した場合、いくらプレゼンが良くても満足度も確実に下がってしまうのです。
他には、周囲条件である、温度、空気環境、騒音、音楽、匂いなども含まれますので注意が必要です。
私が、ある屋外イベントを取材したときのことです。
当日は2月半ば。最低気温1.8度となっており、特に寒さの厳しい日でした。加えて、場所が高架下で日陰。体感温度は1度くらいだったのではないでしょうか?屋外との情報も事前に知らされていなかったため、その場であわてて携帯用カイロを買いに走りました。
イベントでタレントさんが、こたつに入って熱燗を飲んでいるのを見ると余計に寒さが身に染みます。
取材では、寒さはもちろんですが、2月の極寒の時期に「なぜ屋外開催するのか?」という意図が明確に伝わってこなかったところも残念な点です。
これは想定ですが、屋外開催でタレントを呼ぶことで、見物客を集めようという狙いが主催側にあったかと思います。しかし日陰で寒いために、それほど足を止めて見る人は多くなかったような印象です。
タレントさんが、面白いネタをいくら話してもまったくウケず、しまいには「すみません、こんなにウケなくて…」と謝っていました。あまりに寒いと、人は笑う余裕がなくなるのだなということがよく分かった会見でした。
寒さというと、これからの季節は冷房の空調コントロールも難しい季節になってきますね。
ぜひ、プレゼンだけではなく、知覚される環境についても注力していただくことをおすすめします。