ブログ「次世代トッププレゼン」
ブログ一覧
謝罪会見後に株価が上がる会見、下がる会見

ここ数年、増える一方の不祥事会見。
メディアから厳しい批判にさらされながら深々と頭を下げている経営者を見ると、いつも胸が痛みます。
決して他人事ではないからです。メディアの前に立つ可能性は低いものの、一般人でも、社内やコミュニティでいきなり同じ立場に立たされる可能性は少なくありません。そして、こんな場面は、ある日突然やって来ます。
世の中の謝罪会見を見ていると、会見後に鎮火する会見と、さらに炎上してしまう会見があることに気がつきます。どこが違うのでしょうか。
ハーバード・ビジネススクール教授・ビル・ジョージらの著書「オーセンティック・リーダーシップ」で、“効果的な謝罪”と“逆効果を招いてしまう謝罪”の違いが最近の研究で明らかになっていると述べられています。
トップが笑みを浮かべて謝罪した企業は、株価の下落が判明しました。謝罪に誠意がないとみなされたからです。
逆に、悲しそうな表情のトップが謝罪した後、株価は上昇していることが明らかになりました。
悲しそうな表情で行った謝罪は、投資家に「この人は誠実だ」と感じさせて、信頼を獲得することができるのです。
また謝罪会見で業績悪化を外部要因のせいにする企業は、自社の力不足を認める企業より2倍多く、それらの企業の財務状況はその後も引き続き悪化していました。逆に、自らの責任を認めた企業の収益状況は上昇に転じているのです。
これらを理解すると、効果的な謝罪には2つのポイントがあることがわかります。
・まず、自分の非を認める。
・そして心から謝罪の意を示す。
孔子は『論語』の中で、「過ちて改めざる。 これを過ちという」と言っています。
誰でも間違いはあります。間違う事が悪いのではありません。間違いを反省せずに改めない事が、間違いなのです。
人間ですから道から外れるのは仕方ありません。
間違いから反省して正しい道に戻ってくること。
そして大切なことは、単に反省して戻ってくるのではなく、改め、成長する、ということなのです。
リーダーの弱みが、組織を強くする

ある大企業の女性広報部長さんがこうおっしゃっていました。
「社長から責任ある役職を打診されたんだけど、自信がないんですよね」
普通は喜んで受けるような大抜擢のポジションです。しかしその方は「自分にはムリ。断ろうかな」と悩んでおられました。
これはとてももったいないことです。
実は、自分の弱さを認識した上で、そのことを隠そうとしない人のほうが、最強のチームを創れる可能性が高いのです。
100円ショップのダイソーを成功させた創業者の矢野博丈さんも、人前で自分の弱さを隠さない方です。
出演したテレビ番組で、苦難の創業秘話を語ると人目をはばからず泣き、イベントや商談には、頭に巨大ナイフを刺した被り物をして「申し訳ない、こんな格好で社長です」と皆を笑わせながら登場します。
また、雑誌のインタビューでも、虚勢を張らずに弱い自分をさらけ出しています。
「ワシは運が良かっただけ。先見の明とかそんな話じゃありません。運の悪い企業は油断するとすぐに倒産しかねません。改めて考えると、ダイソーも本当に大大夫なんでしょうか。こんなにいろんな歯車がうまく噛み合うということは、逆にそろそろ噛み合わなくなる可能性もあるわけで…。お話ししている間に怖くなってきました」(日経ビジネス2017.12.11)
『THE CULTURE CODE 最強チームをつくる方法』の著者、ダニエル・コイルは、「リーダーが自分の弱さを認め、チームで弱さを共有することが強い協力関係をつくり上げる」と述べています。
一般的に、リーダーは弱さを隠そうとして、強い自分をアピールしがちです。しかし、このような虚勢を張るリーダーの姿を見た部下は、自分も弱さを隠すようになります。こうして組織の中で信頼関係が生まれにくくなってしまいます。むしろリーダーが弱さを隠さないことで、相手との間に「弱さのループ」が生まれ、チーム全体が信頼関係が生まれて、協力しあうような組織になっていくのです。
もちろんいつも弱音ばかりを吐くのは論外です。
しかしリーダーに抜擢されたのは、上司が「この人は任せれば力を発揮する」と潜在力を見極めたからです。
真面目に仕事に取り組みつつ、自身の弱みを隠さないリーダーが率いるチームが、強いチームに育つのです。
『2023 広告界就職ガイド』に「緊張しても話せる面接対策」特集記事掲載
『2023 広告界就職ガイド』(宣伝会議)に、6ページの「緊張しても話せる面接対策」特集記事掲載いただきました。
口ベタで話せない、頭が真っ白になってしまう、重役が出てきてビビってしまった…。そうやって自分自身を伝えきれずに泣いてしまう学生さんもいます。
そんな学生さん方に、緊張を操って、悔いなく自分を伝えられるテクニックを伝える内容になっています。
学生さんだけではなく、通常の面接にも応用できますので、ご興味ございましたらぜひご覧下さい。
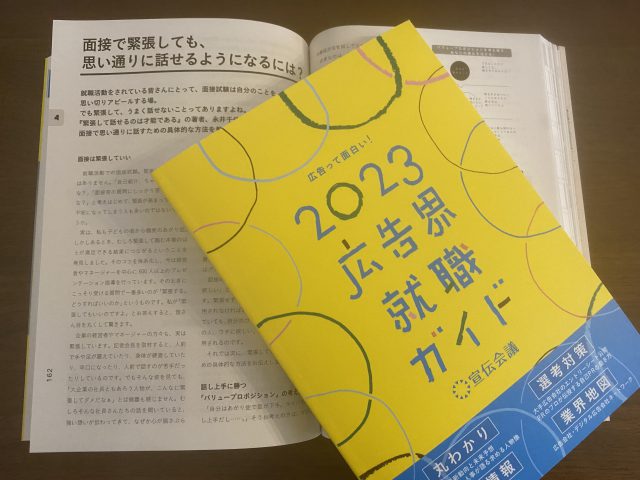
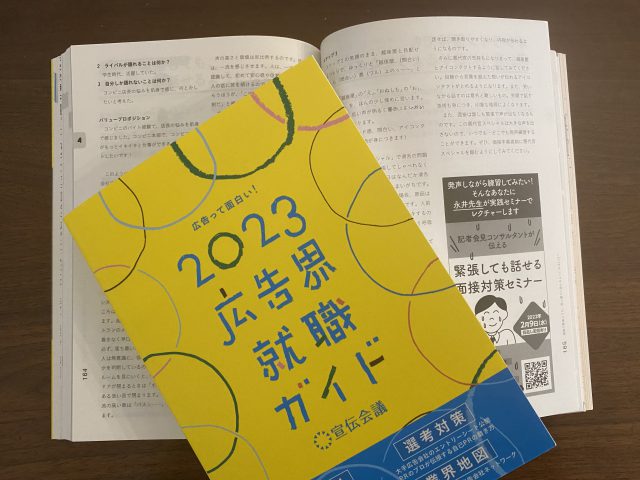
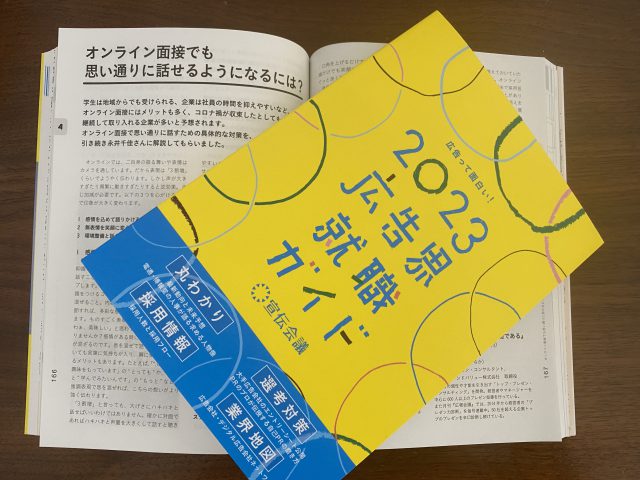
失敗体験を語れる組織文化は、成長する組織文化
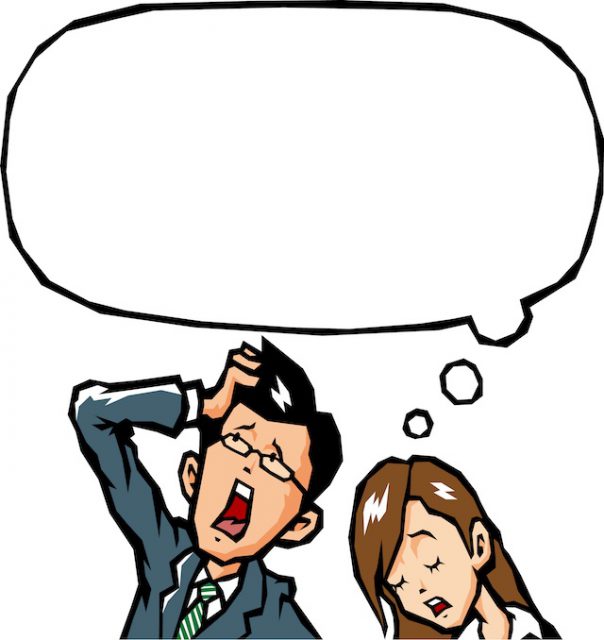
今、組織行動学者エドモンドソンが提唱した「心理的安全性」が注目されています。
エドモンドソンは「『心理的安全性』の高い組織は不正が起こりにくく、成長や進化をもたらす」と述べた上で、心理的安全性の高い組織を作るためのポイントとして、リーダーが「格好つけずに正直に話し、失敗を恐れないこと」を挙げています。
しかし失敗は恥ずかしいですし、隠したくなるものです。誰にとっても失敗を語るのは、気持ちの良いものではありません。そして失敗をネガティブに捉えると、間違いは報告されず、不正隠蔽が起こりやすくなります。
『失敗の科学』の著者、マシュー・サイドによれば、人は失敗について2つのタイプがいると言います。
・「固定型マインドセット」の人…失敗をネガティブに捉えてスルーします
・「成長型マインドセット」の人…失敗をポジティブに捉えて強い興味を示します
ある2人の心理学者が「フォーチュン1000」にランクインした7社の社員を対象に広範なアンケートを行い、各企業のマインドセットを調査したところ、大成功を収めた企業は「成長型マインドセット」の組織文化を持っていることが分かりました。
「固定型マインドセット」の企業は失敗を恐れ、ミスが報告されにくい一方、「成長型マインドセット」の企業では、誠実で協力的な組織文化が浸透していて、ミスに対する反応もはるかに前向きだったのです。
そして組織文化に最も大きな影響力があるのは、リーダーの本気の行動です。社員はリーダーの一挙手一投足をしっかり見ています。
そこで必要なことが、まずはリーダーが率先して派手な失敗談を語ること。これが失敗から学ぶ「成長型マインドセット」の企業文化へ徐々に変革するきっかけとなることです。
この際に大事なことは、失敗を認めること。認めるだけではなく失敗から学んだ経験を語ることです。
これから4月の新年度にかけて、皆さんの前でお話することも増えてくると思います。
つい自分の成功談を話したくなるものですが、多くの社員は、上司の自慢話には本音では飽き飽きしています。しかし失敗談は興味を持って聞くものです。
この機会に「失敗体験の棚卸し」をしてみるのもいいかもしれませんね。
商談で相手が真剣に話しを聞くために

伝え方が上手い人には1つの共通点があります。
それは「聴き手が期待していて、自分しか語れないこと」を話すこと。
どんなに話し方の技術を高めても、自分が話したいことだけを話していたり、他の誰でも語れる内容を話していれば、相手は聞き流してしまいます。しかしたとえ話し下手であっても、聴き手が期待する自分しか語れないことを話せば、聴き手は真剣に話を聞いてくれます。
そのためには、まず相手を知ること。
「そんなこと言っても、相手がどんなことに関心があるのか分からない…」と思われるかもしれません。でもネットやSNSで検索してプロフィールを読み込めば、その人がどんな人で、何に興味がありそうか、おおよその見当がつきます。
またB2Bでは、相手の勤務先の企業サイトたメディア情報を読み込んでおくのも一つの方法です。
伝え方が上手な人は、まず会う前に相手に興味を持って調べています。
とくにカリスマ営業と言われるような人は、商談前に会う相手のことを徹底的に調べ尽くします。
その上で、相手が興味があり、かつ自分だけが伝えられることを話します。だから相手は真剣に話を聞き、結果としてビジネスが成功するのです。
ただこのような準備も、あくまでも「仮説」に過ぎません。
当日は相手の話をよく聞いた上で、予め考えた「仮説」を検証し、もし違ったら別に用意していた二の矢・三の矢の仮説を繰り出しながら話せば、さらに成功する可能性が高まります。
話が伝わらないのは必ずしも話し方の技術の問題だけではなく、事前準備にも原因があるのです。