ブログ「次世代トッププレゼン」
ブログ一覧
No.275「伝える=人が動く」ために必要なこと
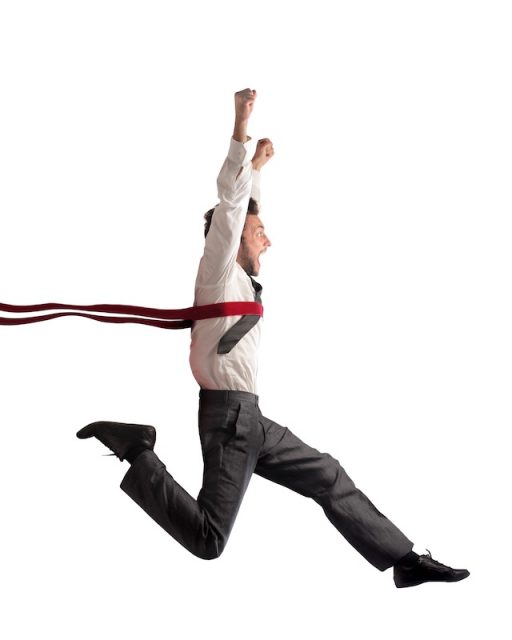
言葉やプレゼンで人に何かを「伝える」のは、人を動かすためです。
人は何かを伝えるときは必ず目的があります。
たとえば「聴き手に行動や考え方、気持ちを、良い方向に変えてほしい」
その思いを言葉や身振りに託して伝えます。
その結果、相手が動いてくれることが「伝える」ことです。
いくらジョブスばりの立派なプレゼンテクニックで話しても、相手がスルーされたら、「伝える」目的は達成されません。
では具体的にどうすれば伝えることができるのでしょうか?
大事なことは、話し手が「なぜそれをしなければならないのか」という大義名分を語ることです。
聴き手は「なぜ自分がそれをしなければならないのか」という大義名分を聞くと、自分ごとに置き換えて考えるようになり、動きます。
「日経ビジネス」2023年1月23号にパナソニックHD社長兼グループCEO楠見雄規氏のインタビューで、楠見さんが米テスラ社の社員さんの言葉を紹介していましたのでご紹介します。
社長就任後に(イーロン・マスク氏と)オンラインで2、3回やり取りしたときのことです。マスク氏が会議に入ってくる前に、社員と少し話す時があった。そのとき「私たちはお金も稼がないといけないが、地球を救うためにやっているのだ」と言うのです。素晴らしい。感動的でした。
社員さんはイーロン・マスク氏の言葉を受けて会社がなぜあるかを腹落ちしているのです。
その人の大義名分は、人の心を動かします。
マスク氏のような大きなスケールでなくともまったく構いません。
「困っているお客さんの力になろうよ」
「この地域の人たちを助けたいんだ」
こんな身の丈のことでもいいのです。
皆さんも、ご自身なりの大義名分を考えて言葉にしてみることをおすすめします。
No.274 広報の言うことを聞かないトップ。どうする?
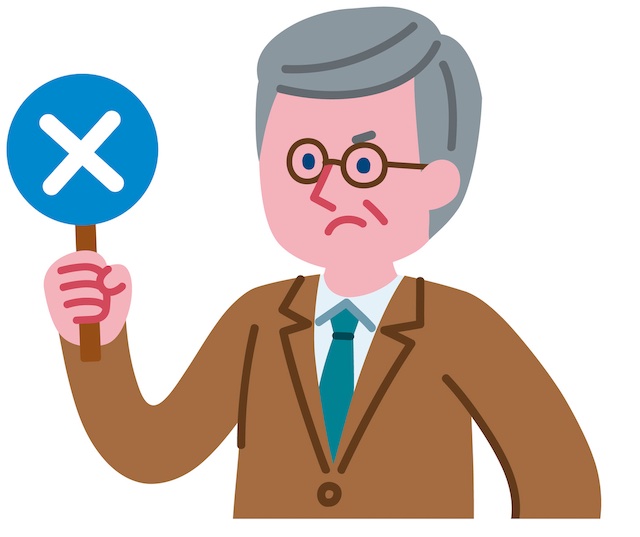
「社長がものすごく話しが下手。プレゼンの練習もしない。改善しましょうと提案しても変えてくれない。どうにかできないでしょうか?」
広報担当者さんのよくあるお悩みです。
特に難しいのは、トップご本人に自覚が全くない場合です。
恥ずかしいと思っているのは周囲だけ。
本人は「これでいい。そこそこイケてるよ」と思っている。変える気はサラサラありません。
結果、広報担当者が何を言おうが、全く聞く耳持たず、なのです。
部下の話を全く聞かないから、こうなってしまうのです。
こんな聞く耳持たずのトップを変えることなんて、できるのでしょうか?
一つだけ確実に変えられる方法があります。
実はこんなトップでも、必ず言うことを聞く相手がいます。
まずは大株主。次に社外取締役です。
なぜか社長が素直に彼らの話を聞くのかと言うと、大株主と社外取締役は、社長の人事権を持っているからです。
社長は毎年の決算のたびに、株主から会社の経営を任せてOKかを判断され、社長に指名されます。
でも大株主が細かいところまで経営の状態をいちいちチェックするのって、大変ですよね。
そこで株主から経営のチェックを任される(委託される)のが、社外取締役なのです。
どんなに威張っている部長さんでも、自分の人事権を持っている上司の役員さんに怒られたら、素直に言うことを聞きますよね。
社長と大株主や社外取締役の関係も、これとまったく同じです。
ただ広報担当者が大株主に直接お話しして相談するのは、あまり現実的ではありません。
そこで現実的なコンタクトは、社外取締役になります。
2021年改訂の東証「CGコード」によれば、独立社外取締役は「社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべき」「ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること」とありますし、会社の風土を変える機能も期待されています。
実際に私がご支援させていただいた企業様でも、社外取締役から『社長の話し方が良くないのでなんとかしてください』という意見が上がりコンサルティングをご依頼いただいたトップも何名かいらっしゃいます。
社長の行動を変えてほしければ、まず「トップが言うことを聞く人を使う」ことが大事なのです。
ただ広報担当者が社外取締役に相談したことを社長に気づかれると、相談した担当者はとても怒られるかもしれません。
ですのでこの手段は、絶体絶命な時に最後の手段としてとっておきましょう。
No.273 声が良くなり、二重あご、ほうれい線が消えるボイストレーニングの方法

ある日鏡を見たとき、ほうれい線や、二重あごに気がつくことってありませんか?
年齢が若くても、二重あごだと一気に老けた印象になってしまいます。
じつはボイストレーニングをすると、表情筋もしっかりと鍛えることができ、若々しい印象を与えることができます。
ボイストレーニングの中で特に筋力アップやマッサージ効果の高いものは、「リップロール」です。
リップロールは、声だけではなく、顔の血行や表情筋も鍛えてくれる最高のボイストレーニングです。
今日は、誰でも簡単にできる「リップロール」の方法をお伝えします。
【リップロールの方法】
(1)軽く口を閉じる(上下の歯は軽く離れています)。
(2)口を開けて息を吸う
(3)口を閉じ、唇をほんの少し突き出し、閉じた唇の間から息を出して唇を「ブルブル」と振動させる。
※ポイント:「ブルブル」はできるだけ長めに続けてください。上手く出来ない場合は口周りをリラックスさせて、左右の人差し指で少しずつ口角を寄せたり上げたりしてみてください。
(4)(3)が続くようになったら、「ウ~」と歌うように、声帯を反応させながらリップロールを行う。息が切れたら息継ぎしてください。
1日3分くらいでOK。継続すれば声が良くなるだけでなく、表情も若々しくなります。
No.272 手振りで説得力を高めるためのちょっとしたコツ

「人前で話すのが苦手なんですけど、プレゼンすることになっちゃいました。説得力を上げる方法はないですか?」
こんなご相談を受けることがあります。
内容は良く出来ていても、プレゼンでいかにも苦手な感じが出ると、説得力や安心感が大きく落ちてしまい、せっかくのいい内容が聴き手に伝わりません。これはもったいないですよね。
そこで時間をかけず簡単に説得力が上がる方法があります。
それは手振りを使うこと。
手振りの基本は、ろくろを回すような雰囲気で両手を広げて体の前に出すことです。
内容に合わせて手を動かすと良いでしょう。
ただここで多くの人が間違えるポイントがあります。
それは、手を速く動かしすぎないこと。
ほとんどの方は、本番になると話すことに精一杯。手振りにまで気が回りません。この結果、手振りしているのですが、セカセカと雑な動きになっています。
手振りは、ゆっくり動かすことで初めて落ち着きが感じられて、説得力が宿るのです。
参考になるのは歌舞伎や能の動きをイメージすること。でもこれは修練が必要です。
そこでプレゼンに余裕がなくても、ゆっくりと手振りができるようになるコツがあります。
それは、ある程度の重みを感じる容量のペットボトルを持ちながら手振りを練習しておくことです。
ペットボトルを持って手振りを行えば、重量感のある丁寧な動きを感覚的に覚えることができます。
そして今度はペットボトルを外して、その重量感がある手振りを再現して、身体で覚えればOK。
手振り一つで、言葉を超えた世界観が表現できるようになります。
ぜひ次回のプレゼンではお試しください。
No.271 リーダーが自分らしく話せば、メンバーのやる気が引き出される

「我が社の新しいパーパスも決まりました。社員の前でもっとたくさん話そうと思います」
こうお話しされるトップは、もともと話が苦手な方でした。
しかし心機一転して、全国各地の支社を訪れて、積極的に社員に向けてお話することにしたそうです。
パーパスとは、「会社が向かう方向」を示したものです。
トップが何を目指すのかをしっかり語れば、社員のやる気を引き出すこともできます。
ただ、ここで注意していただきたいことがあります。
それは「腹の底から、自分らしく語る」。
上手でなくても、ぜんぜんOKです。
むしろ危険なのは、ムリをしてジョブズ風やTED風に語ることです。
なぜなら人の脳は、相手のウソを直観的に見抜く「レゾナンス」という仕組みを持っているからです。
人は「この人、何か偽っているかも…」と無意識に感じた途端、その人の信頼度を一気に下げます。
だから自分らしく、嘘偽りのない態度で話すことが大事なのです。
アメリカの経営学者・ビル・ジョージは、自分を偽らずにありのまま振る舞うリーダーシップを「オーセンティック・リーダーシップ」と名付けています。そして人は自分らしいリーダーに強い絆を感じるのです。
大企業の社外取締役も務める成蹊学園・学園長の江川雅子氏は、これからのリーダーに求められる資質や能力について下記のように述べています。
ある会社で社長指名を受けたリーダーが、「社員の心に灯をともしたい」という抱負を述べたのが印象に残っています。以前は、より具体的なスキルや能力がリーダーの条件として挙がることが多かったのですが、このように多様な人々の心を動かすリーダーがますます必要になっています。
(ハーバード・ビジネスレビュー 2022年11月号)
年始から新入社員が入社する4月にかけてのこの時期、トップは社員の前でお話しする機会が多くなります。
また、トップでなくともチームのリーダーをされている方も、目指すべき方向性をメンバーに話さなくてはならない時期です。
ぜひ自分らしく、誠実に、腹の底からお話いただくことを願っています。