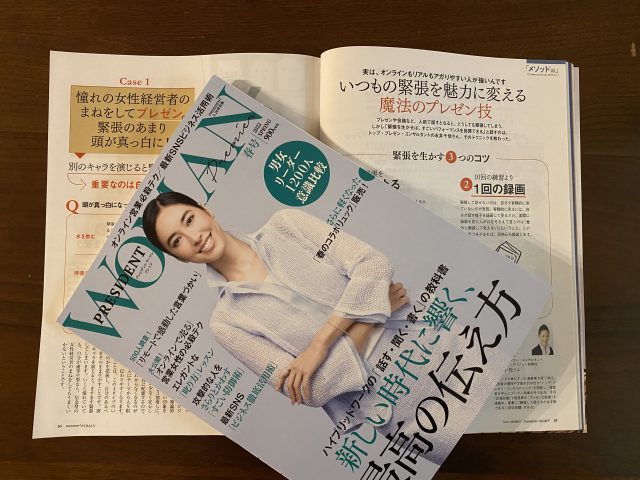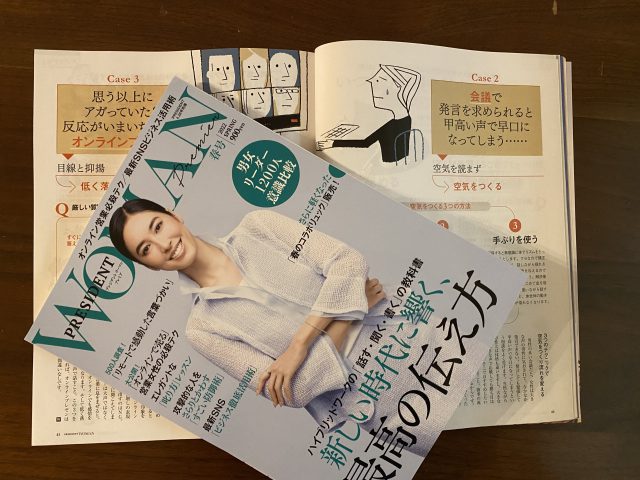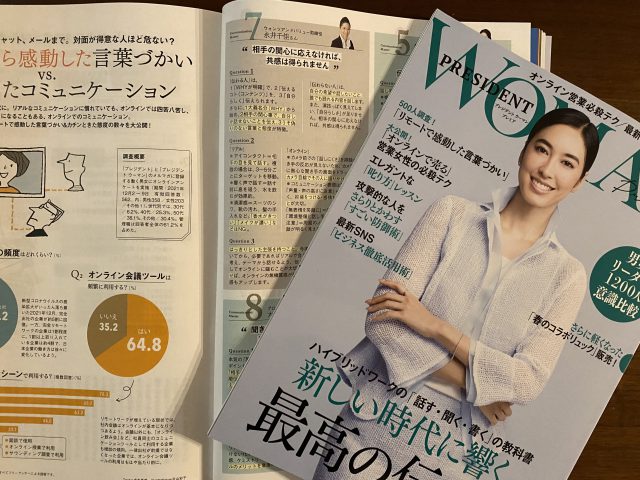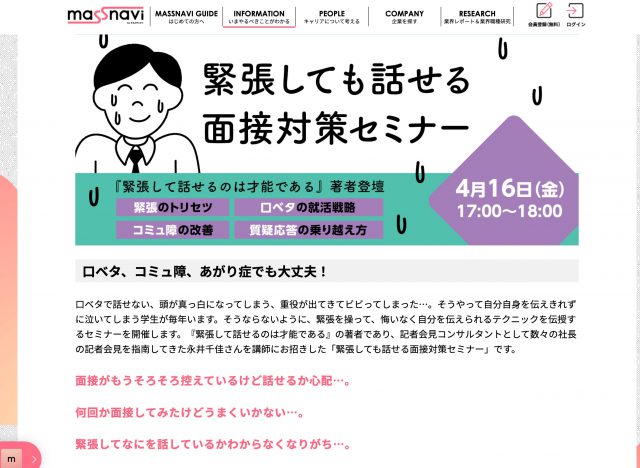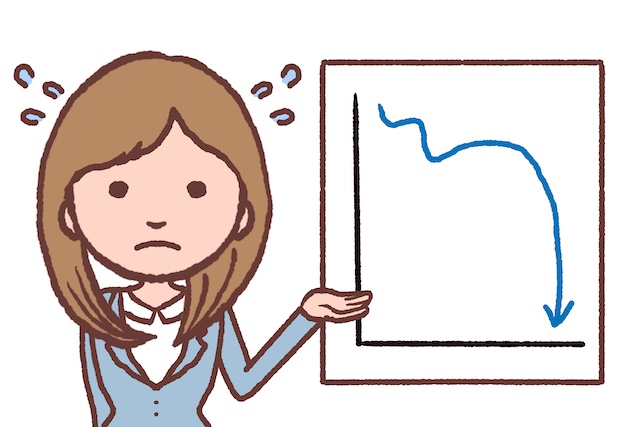
「口ベタでプレゼンが苦手なので、できれば上手になってからプレゼンしたいんです」
このようにおっしゃる方がいらっしゃいました。
「上手になってからプレゼン」と言っていると、いつまで経ってもプレゼンはできません。
人が成長するために必要なのは、アウトプットして、結果から学ぶこと。
プレゼンも本番を経験することで上達します
プレゼンで聴き手の反応がわかります。その反応を元に「どうすればもっと良くなるか」もわかるのです。
他人の考えや頭の中は、絶対にわかりませんよね。でもアウトプットすれば、他人の反応が見えます。こうして自分が知らないことがわかります。知らないことを知ることが、自分の限界を超える助けとなり、成長につながります。
たとえば、営業のプレゼン。Aさんはプレゼンしたのに上手く契約がとれませんでした。
「なぜ上手くいかなかったのか」と振り返ってみて「お客さんが『困っているのはソレじゃないんだよね』って言ってたなぁ。そうか、聴き手の課題が把握できていなかったんだ」ということにAさんは気がつきました。Aさんは「顧客の悩みをまず理解しなければ」という学びを得ました。次からは、顧客のところに行く回数を増やし、顧客とコミュニケーションをとることで、顧客の悩みをまず理解して、それを解決するプレゼンを心がけるようにできます。
この場合、Aさんの失敗の原因は「プレゼンが下手だったから」ではありませんよね。
「顧客の悩みを把握できていなかった」ということです。
「上手になってからプレゼン」と考えてハウツー本を読んでプレゼンの練習をしていたら、こんなことには気付きません。
まずアウトプットして、そこから学ぶ方が学びも大きいのです。
教育理論家のデービッド・コルブは、この営業のようなサイクルを「一度だけではなく何度も循環させることが成長を促進する」と言います。これがコルブの「経験学習サイクル」といわれるものです。
プレゼンが上手になるための第一歩は、まず思い切ってプレゼンしてしまうことが大事なのです。