ブログ「次世代トッププレゼン」
ブログ一覧
気まずくなりがちな質疑応答を盛り上げる方法

「質疑応答で質問がないと気まずい雰囲気になります。そういうときどうすれば良いでしょうか?」
という質問を受けることがあります。
質疑応答は、話し手にとって本編の内容を補足する大事な時間です。記者会見では質問に答えることでPR効果も出ます。質疑応答こそ、勝負の場。
ただ聴き手の立場になると、「質問が思い浮かばない」「緊張する…。誰か最初に手を挙げてくれないかな」と考えて待っていることもあります。
2019年9月30日に行われた「宮城県×ポケモン『ラプラス』共同観光キャンペーン記者発表会」の宮城県知事・村井嘉浩氏のプレゼンでは、質問がない中で、上手に質疑応答を活性化させていました。
村井知事は、何度か質問を募っても静まりかえる会場に向かい、ニコニコしながら「ちなみにマスコミの皆さん関心があるかと思いますが」と前置きし、「2020年の目標ですが宮城県では来年1年間宮城県では来年1年間で7000万人の観光客動員、のべ1000万人の宿泊客、4000億円の観光消費を目指しています」と、自らPRを始めました。
質問がないことを上手く利用し、言うべきことを伝え、PR漏れがないようにしていたのです。
静まりかえる質疑応答は気まずい雰囲気になりがちですが、せっかくメディアが集まっています。質疑応答を止めるのはあまりにももったいないですよね。慌てず騒がず、「ちなみに関心あるかと思いますが」と、ひとこと入れてから言いたいことをぬかりなくPRする臨機応変な対応は「さすが政治家」と思いました。
これは企業のプレゼンでも応用できます。質問がないと気まずい雰囲気になってしまいがちです。そういうときのために話す内容を準備しておき、「よくある質問ですが」と前置きして話すと、次の質問に繋がりやすくなります。ぜひお試しください。
ちなみに村井知事の会見は、村井知事がラッパーになったりとサービス精神旺盛なプレゼンでした。
ご興味ある方はぜひこちらの記事をご覧下さい。
肺機能が衰えがちな冬は、声も出なくなる。そこで対策

こんなお悩みを聞くことがよくあります。
「最近、声が出なくなってきた」
「話していて、すぐに息切れする」
原因として、肺機能の衰えがあります。
2015/1/31の日本経済新聞の記事「健康:肺の衰えに気をつけて」によると、
「肺機能の維持には定期的な運動習慣が大切。ただ歩くだけでなく、スポーツジムなどを利用して上半身の筋肉をしっかり鍛えることが必要」
つまり運動不足になると呼吸に使う筋肉の衰えを招いてしまうのです。
冬になると、寒くて外を出歩きたくない日々が続きますが、歩かないとさらに身体が動かなくなり、肺機能が衰えます。
この肺機能の衰えは、声にも影響します。良い声は、良い息を流すことで得られるからです。
風邪などで数日間運動しなかっただけで、仕事で話をすると声にパワーがまったくなくなる経験をした方も多いと思います。
運動も大事ですが、呼吸することでしか鍛えられないインナーマッスルを鍛えることも大事です。どうしても仕事で忙しくなってしまい、運動ができないときは、ちょっとの空き時間や道を歩くときに「横隔膜ブレス」を行って、横隔膜を鍛えて良い呼吸を維持するようにすることをおすすめします。
★★ 横隔膜ブレストレーニング ★★
呼吸だけで横隔膜インナーマッスルを鍛えるトレーニングです。
(1)肋骨のすぐ下あたりに手を当てる
(2)顎を下げて口を開け、思い切り息を吸う
ポイント:肩が上がらないように。お腹が風船のように張る感じを手で確認すること。
(3)口を閉じ、唇に針一本通るくらいの隙間を開けて頬と鼻の下がパンパンにふくらましながら5秒息をはき、6秒目に止める。
ポイント:頬と鼻の下がパンパンにふくらむように。口の前にティッシューをかざすと地面と平行になびくくらいの呼気です。お腹はできるだけ張った状態を維持します。
(4)再び口を開けて2から繰り返す。5回行う。
身体を使わないことが多い冬だからこそ、お試し下さい。
–
苦しい「喉締め」や「力み」を抜くための方法
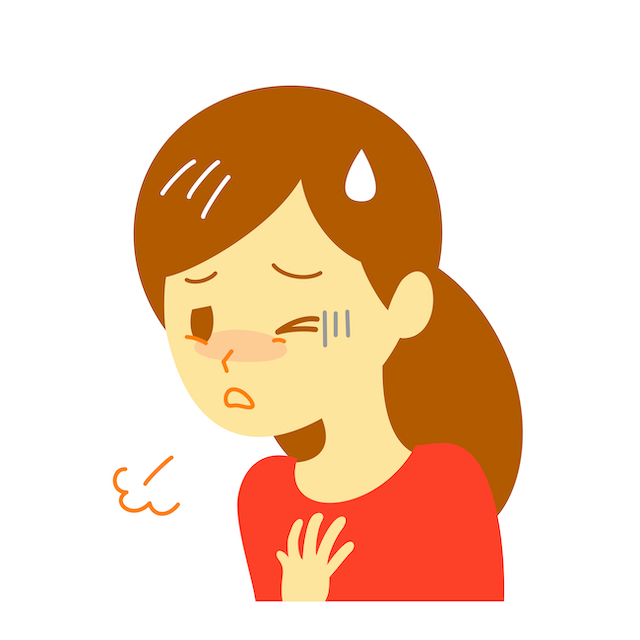
言葉に気合いが入りすぎて喉を締めて出してしまったり、声に力みが入ってしまう方が多くおられます。
話すことに一途で、伝えようと一生懸命になるのですから、当然のことだと思います。
だから、「つい力んで身が入ってしまう」ということは、冷めていたり、感受性が弱かったりする人よりは何百倍も可能性があり、悪いことではありません。
問題は、力むと声帯に余分なストレスがかかってしまい、声嗄れの原因になってしまうことです。すぐ休めば良いのですが繰り返すと声が戻らなくなってしまいますので注意が必要です。話す量も多い政治家は、ガラガラ声の方が多いのもその理由からです。
そこで、ついつい力んでしまう方向けの練習方法があります。
ガラス磨きをするときや眼鏡を拭くとき、「は〜」と息を吹きかけて磨きます。その息で発声するのです。
方法は、窓ガラスを「は〜」と磨きながら話し、またすぐに「は〜」と磨いて話す、という練習を繰り返します。窓ガラスもキレイになりますので一石二鳥です。
コツは、「は〜」の息のまま発声することです。少しずつ、力みがとれて、楽な発声に変わっていきます。
次の段階は、「フクロウ」の発声法です。フクロウが「ホー」と鳴くまねをします。
これは意外にコツがいります。「ホー」と言うとき感情を込めないことです。一生懸命な人ほどフクロウの鳴き声に感情がこもってしまいますので、あくまで本物のフクロウが鳴いているように「ホー」と鳴きます。
以上が出来るようになったら「ホー」を、ロングトーンで「ホーーーーーーー」と伸ばしていきます。
最初は大きな声が出ないので欲求不満になってしまうかもしれません。しかし、大きな声を出して「スッキリした」というのは大抵喉に負担がかかっていることが多いものです。発声に「手応え」を求めてはいけないということです。
この「ホー」が上手く出来るようになると、話しているときに声の力みが取れていきます。
一生懸命な気持ちはそのままに、発声部分はあえて「そらす」という方法も必要なのです。
滑舌悪化の原因「子音」は、ピンポイントで克服せよ

「滑舌が悪く聞こえる」という悩みを抱える方、多くおられます。
滑舌が悪くなる原因は、子音が上手く言えていないこと。
子音は、一つずつピンポイントで克服することが必要です。
ピンポイントで意識せずにたとえば早口言葉の練習すると、いつも同じ子音でつまずいてしまい、滑舌の悪さが癖になります。「繰り返し練習」が「つまずく練習」になっているのは、もったいないですよね。
子音をどのようにしてピンポイントで克服するのか。
今日は多くの方があまり得意ではない[n]の子音についてお伝えします。
[n]の発声は、口が少し開いた状態で、舌が上がり上アゴに舌先がべったりとつきます。とくに舌の筋肉が弱いと、舌先が上アゴにしっかりつかず、[l]に聴こえてしまうか、舌が口腔内で空振りして母音しか聞こえないこともあります。
「バナナ」だと、「バララ」とか「バアラ」と聴こえ、滑舌が悪く聞こえます。
[n]の子音は「第六の母音」とも言われています。母音の特徴は音を伸ばせることですが、[n]も「n〜〜」というように、音を伸ばすことができるからです。[n]が母音と同じように響かせることができるようになると、滑舌の悪さは改善できていきます。
[n]の子音は、伸ばすことで簡単にトレーニングすることができます。
【nのトレーニング】
①口を少し開けて息を吸う
②舌の全面を上あごにぴったりつける
③「n〜〜〜〜〜」と伸ばす
①〜③を10回繰りかえす。
舌の筋肉が鍛えられ、[n]が空振りせず、響くようになってきます。
プレゼンで行う呼吸の方法

私自身が発声で一番気をつけていることを一つだけあげるとしたら「呼吸」です。
声を出すのだから、「声の高さ」や「抑揚」と思われるかもしれませんね。もちろん、それらのことも大事です。
しかし、一番難しいのは呼吸です。呼吸の問題は、経験を積み重ねるとより効果も上がりやすくなるのですが、同時に課題が増えてくることも大きな特徴だからです。
呼吸の基本は、横隔膜という肺の下にあるドーム型をした呼吸のための筋肉を使えるようにすることです。横隔膜を使えた呼吸ができるようにすれば、専門家が行うような難易度の高いボイストレーニングは必要ないとも言えます。
しかし一方で、難易度の高いボイストレーニング法をこなせていても、なぜか横隔膜が使えていない方が多いのも事実。これでは、一生懸命トレーニングしたとしても効果は得にくいと思います。
つまり、発声にとって「横隔膜を使えない」ということは、足腰がしっかりしてないままスポーツをするようなものです。
「息を吸う」というと、簡単なように思えますが、結構エネルギーを使います。不慣れな人が呼吸を意識しながら話すのは体力的にキツいものです。
以下に、話しながら横隔膜を使った呼吸を扱う方法を具体的にお伝えします。
【基本】息を吸ったときに、下腹(へそ下9センチくらいの場所を意識)を張り、張ったまま息をはいていきます。この呼吸を繰り返しながら、発声していきます。
【プレゼン時】文章ごとに、息を吸いながら話す。話しているとき、下腹はできるだけへこまさないようにする。
不慣れな状態でたくさん吸おうとすると身体が力んでしまいますので、ムリに長いセンテンスを話そうとせず、「少しだけ吸って短く話す」を繰り返してください。