ブログ「次世代トッププレゼン」
ブログ一覧
オンラインの質疑応答で困ったときにはこの言葉

最近、新型コロナウイルス感染症の流行によりオンラインでの会見が増えていますね。
オンライン会見ではライブで質疑応答を行う際に動画が残ってしまうので、不用意な発言には要注意です。
一方でどんな質問にも「詳細はお答えできません」では、印象は悪くなります。
質問する方の中には、残念ながらこちらが知らないような自分の専門知識を多用してマウンティングしたり、明らかにつぶしにかかる相手もいます。
そういう相手に対して、とても良い答え方をしているトップがいましたのでご紹介したいと思います。
「勉強不足なのですが」
有名なトップでもあったので、業界の知識はそれなりにお持ちだと思うのですが、知ったかぶりをしない謙虚な姿勢に好感を持ちました。
「勉強不足なのですが」は、質疑応答で困ったときに使える、好感度を高める良いフレーズです。ぜひ覚えておいてください。
「プレゼンが時間超過しても聞きたくなってしまう理由」

「プレゼンが時間超過しても聞きたくなってしまう理由」
プレゼンで時間超過すると、ほぼ確実に満足度が下がるものです。
しかし先日、時間超過しても「もっと聞きたい」と思ってしまったプレゼンを見てきました。
2020年1月21日に行われた、くら寿司「グローバル事業戦略発表会」での田中邦彦社長のプレゼンです。
冒頭、プレゼンの調子はいま一つだったのですが、開始3分後に「明治維新が成功したのは『この国は滅びる』というコンセプトがあったから。企業経営も同じ」と語った瞬間にスイッチが入りました。幕末志士たちの魂が乗り移ったかのように熱く語り始めたのです。
「ホラを吹く経営者は多い。私はホラが大嫌いだ。言ったことは必ずやる」
「2020年中国進出、2030年に売上高3千億円、全世界で1千店舗を目指す」
と宣言した後は、日本経済界を憂い、喝破しながら、話しが止まらなくなりました。
昨年、念願のナスダック上場を果たしたくら寿司。
「ここまで来るのに涙を流すことがたくさんあった」と話しながらも、その目線の先にあるのは「世界」。田中社長の大きな夢に共感した会見でした。
もし、話し手が熱い想いを持っていたならば、その想いを語り尽くすことが強い説得力につながるのです。
質疑応答こそ、説得力の差が出る

こんなご質問をいただきました。
「質疑応答で、質問を打ち切るタイミングはいつでしょうか」
質問が尽きないということは、会見が盛り上がっているということですし、聞き手の問題意識や当事者意識が高い好ましい状況です。
私の経験では、問題意識の高い記者たちは彼らは良い質問を重ねながら問題の核心に迫っていきます。そして話し手が真剣に質問に答えることで聞き手の問題意識が刺激され、さらに良い質問が出る、という良い循環が生まれます。このような「知的コンバット」とも言えるような場になることこそ、記者会見における質疑応答の神髄でしょう。
話し手と聞き手の高い問題意識と良い質問による議論は、より良き世の中にするためにも重要です。
ただせっかく質問が尽きない状況となっても、どこで打ち切ったらよいのか判断に迷うところです。
会場の時間制限もあるかもしれません。
時間が長引けばトップの不用意な発言を心配する人もいるでしょう。
しかしそれでも、もし質疑応答が「議論すべき良い場」となったと判断したならば、時間の許す限り質問に答えることが大切だと考えます。
私が今まで取材してきた記者会見の質疑応答や囲みで、司会者や広報担当者が質問を打ち切ろうとするのを制して「質問が尽きるまで、全て答えます」と言ったトップは数えるほどしかいません。
最近では、ストライプインターナショナルの石川康晴社長とZHDの川邊健太郎社長です。このお二人は、会見が「良い場」となっていると判断した上で、担当者を制して質問に答え続けると意思決定を行いました。ご自身のビジネスに対して強い責任感を持ち、何を聞かれても明快でした。また良い質問を受け続けることで、彼らの答えも相対して深まっていくことも感じられました。
一方で予め質問を打ち合わせておいたり、質問を想定して回答を用意しているトップもいます。想定問答を用意するは良いことですが、「想定問答集」を読みながら回答するトップもよく見受けられます。質疑応答までカンペを見るようでは、説得力は格段に下がってしまいます。想定問答は確認にとどめて、ぜひ自身の言葉で語っていただきたいものです。
プレゼンでは腹を据えて何でもやるのがリーダー

「人前に出ると恥ずかしくて、どうしてもぎごちないプレゼンになってしまう」
そうおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
プレゼンの目的は、話し手がリーダーシップを発揮し、聴き手の考えが良い方向に変わり行動することです。
ぎごちないプレゼンをしてしまうことで本来の意図が伝わらず、聴き手の行動が変わらないのであれば、そのプレゼンは失敗です。
村井嘉浩宮城県知事の会見を取材したときのこと。村井知事のプレゼンは「MC村井」に扮してラップを披露したり、ゆるキャラに抱きついたりとサービス精神を発揮していました。しかし村井知事は陸上自衛隊出身の硬派。「チャラチャラは苦手」とのこと。
ただ、「宮城の観光ためなら、何でもやる」と腹決めし、「還暦近いが、歯を食いしばって頑張った」「笑ってください」と話していました。
リーダーシップとは、変革を成し遂げるために、率先してバカになって踊るものであることを良く知っている人の言葉です。
私はここに「伝えきる」リーダーシップの源泉があると考えます。
宮城県を良き方向に変革するという大義名分のためなら自分を捨ててどんなことでもやるのが村井知事のリーダーシップが伝わってきました。
伝えきる気持ちが恥ずかしさを上回ったとき、聴き手の心が動き、良い方向に行動に変わるのだと思います。
音を立てて息を吸う残念なプレゼンへの対処方法
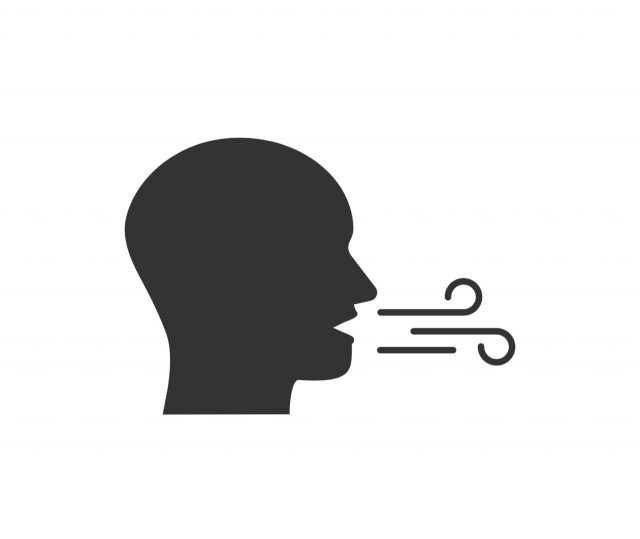
プレゼンで、息を吸うとき「シーッ」と音を立ててしまう方がよくいらっしゃいます。
具体的には、「虫歯かな?」と気にして確認するときとか、男性に多いのですが、ラーメンのような食べ物を食べたあとの息を吸うときの音に似ています。
これは、話し手が不安を感じて話しているような印象を与えますし、何より聞いていてあまり爽やかではありません。
出来れば、息を吸うときは音が立てない方が良いと思います。
加えて、音を立てて息をすうことをおすすめしない理由はもう一つあります。
それは、口の中が狭くなってしまうことです。
口の中が狭くなるとなぜいけないのでしょうか。それは、良い声が出なくなるからです。良い声で話すための条件は、「口の中」が広いことなのです。
(詳しくはこちらのコラムをご参照ください。→ http://nagaichika.jp/20200108-2)
話すときに「シーッ」と音をたてることが癖になっている方は、口の中が狭くなり良い声が出ていない可能性が高いので、意識して音をたてないようにすることをおすすめします。
また、癖になっていなくても、話すときにストレスを感じたり、強く緊張すると、アゴが固くなったり歯をかみしめてしまうため、口の中が狭くなりがちです。
記者会見の質疑応答で、記者から厳しい質問を受けると「シーッ」と音をたてて息を吸うトップを見かけることがよくあります。こういうときに「シーッ」という息の吸い方をすると、声も小さくなり、余計に悪い印象を与えてしまいます。加えて「シーッ」と息を吸っている人に対して、聴き手は「自信がないのだろうか」と不安を感じやすくなります。
対策方法は、落ち着いてアゴを下げながら息を吸うことです。
アゴを下げるだけで、口の中の空間を確保することができ、「シーッ」という音はしなくなります。
必ずできるコツは、「冷たくなった手を暖めるときの息」で「はあ〜」と息をはき、そのままの状態を変えずに息を吸ってください。
【呼吸のやり方】
プレゼン中に行ってください。
(1)アゴを下げて「手を温めるように」ふわーっと息をはく。
(2)アゴを下げたまま、ふわーっと息を吸う
(3)アゴをゆるめながらそのまま話す
※緊張で硬くなっていると一回では上手くいきません。2〜3度意識して繰り返すと上手くいきます。
この呼吸方法を身につけると、良い声がでやすくなります。
アゴを下げて、よく息を吸ってお話してください。安心感、信頼感、説得力が上がります。