ブログ「次世代トッププレゼン」
ブログ一覧
No.290 額縁パーパスにならないために

「会社のパーパス」を語るリーダーが増えています。
パーパスとは、会社の存在意義のこと。会社の本質を一言で表現したものです。
最近、さかんにパーパスが語られるようになった背景には、働く会社を決めるときにパーパス重視の人々が増えてきているためです。
入社時や転職時に「パーパスを年収よりも重要視する」という方が半分以上いる、という調査もあります。
(「ウォンテッドリー、企業のパーパスと採用に関する調査結果を発表」2022年7月11日)
いまやより良い人材に選んでもらうためには、パーパスは不可欠。
パーパスを掲げるトレンドが生まれているのです。
しかしパーパスを作っても、数ヶ月も経つと経営幹部でも「ウチのパーパスなんだっけ」となってしまうケースは少なくありません。本来パーパスは自分の言葉で語るべきなのに、プレゼンでパーパスを読み上げているトップもいたりします。
一橋大学ビジネススクールの名和高司客員教授は、このようなパーパスを「額縁パーパス」と名付けています。
額縁に入れて飾っているだけで、身についていない…。
リーダーが、台本のように額縁パーパスを棒読みしていたら、嘘くささを感じてしまいますよね。
パーパスは会社の本質です。
リーダーが自然に出てくる自分の言葉で語って、伝えていくものです。
パーパスを伝えるときに単なる綺麗ごとではなく、より説得力を高めるには、具体的な言葉を入れると話しやすくなります。
サイバーエージェントは2021年に「新しい力とインターネットで日本の閉塞感を打破する」というパーパスを制定しました。藤田社長は、パーパスを次のように語っています。
インターネット産業は成長を続け、新しい仕事も増えて、若い人が活躍している。しかし自分達の外に目を向けると多くの先送り世代が居座り、若い人の閉塞感につながっている。既得権益も存在する。
ビジネスも日本の閉塞感はこれからも続く。現状の延長線にある限りそれを打破する動きは進みそうにない。しかし民間企業としてやれることはある。情熱を持って、熱狂しながら変えていきたいと思える問題があれば、その状況を打破するのは自分達の役割の一つだ。
(ハーバード・ビジネスレビュー 2022年6月号)
パーパスは飾っておくものではありません。
ましてや暗記するものでもありません。
ぜひ、ご自身が腹の底から信じることを、具体的で力強い言葉で語っていただきたいものです。
No.289 嗄れをなくす発声法
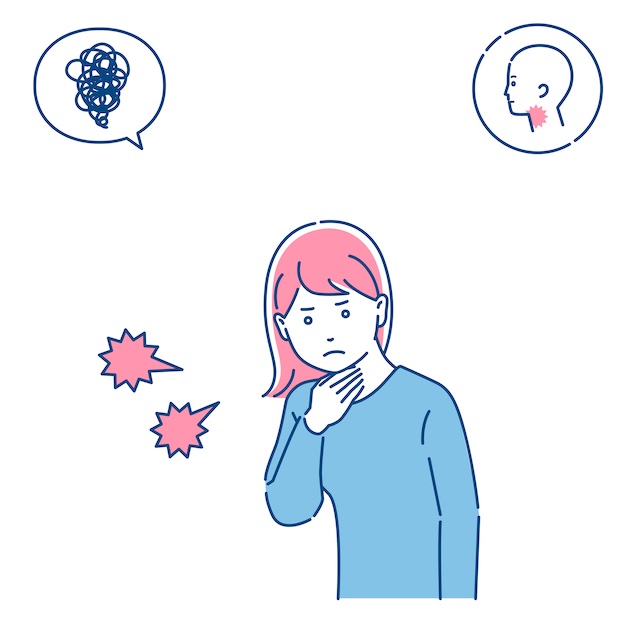
人前で話すとすぐ声が嗄れてしまう方、結構多くおられます。
それに話している途中で声が嗄れるのは話しにくくて困りますよね。
一方で声が嗄れない人もいます。
声が嗄れる原因は、喉に余分な力みがあるからです。
ただ「つい力が入ってしまう」ということは、醒めていたり、感受性が弱かったりする人よりは何倍も感動する話になって相手に伝わる可能性も高いので、必ずしも悪いことではありません。
ただ、声嗄れを繰り返しすぎるとガラガラ声に移行して定着してしまうことがあるので、要注意です。長時間大声で話す政治家や八百屋さんなどに声が嗄れている方が多いのは、限界を超えて無理に声を出し続けた結果です。
声嗄れは力みが原因なので、声嗄れを防止するには、声帯をリラックスさせるトレーニングをすると良いでしょう。
ポイントは、声帯を緩めるための「息を使う」ことです。方法は以下です。
(1) ガラス磨きや眼鏡を拭くときガラスに「は~」と吹きか
けるような息をはく
(2) 息を吸って話す
(3) (1)(2)を繰り返す
「は~」と暖めの息をはくことで声帯の力みがとれてきます。
簡単ですのでお試しください。
本番中声が嗄れてしまった場合は、水を飲むことで応急処置ができます。
声が嗄れやすい方は、水を用意してプレゼンに臨みましょう。
No.288 プレゼン苦手の克服法

「私、プレゼンが大の苦手。やったら絶対失敗しちゃいます。できれば一生やらないで済ませたいです…」
こんな方がいらっしゃいました。
でも社会人ならどんな人でもいつかはプレゼンする機会は訪れるものです。
本来は「これやりたい」「楽しそう」と思って取り組む方が成功しやすいと言われています。
では「仕方ないからやる」のは、やっぱり無駄なのでしょうか。
知人に誘われて、田んぼの草取りの手伝いに伺ったことがあります。当時の私は、「庭の草取りだって面倒なのに、なんで田んぼの草取りをしなくてはならないの?」と思いました。
なんとなく草取りを始めましたが、つまらない単純作業の連続です。
でもやっているうちに少しずつ雑草の抜き方や水田の動き方のコツがつかめて、気持ちに余裕が出てきました。そうすると、「どうするともっと効率が良くなるか」、「身体を上手く使うにはどうすればいいか」など、工夫しながら作業するようになります。ふと楽しんでいる自分に気がついたのです。その瞬間、自然への畏敬の念と共に、幸せな気持ちがわき上がってきました。
江戸時代初期の思想家・鈴木正三(すずきしょうさん)は、「何の事業も皆佛行なり」 と考え、「ただ無心に行動することで気づきが得られる」と言います。
正三の時代は、悟りを開こうと思えば寺院にこもって修行しなくてはいけないと考えられてきました。しかし正三は、日々の仕事こそ仏行であり、仕事をすれば自動的に世の中に貢献することになり、ただ仕事に感謝して働けば悟りが開けるということを言ったのです。
自分が見えている世界は、これまでの経験からくる前提や思い込みから出来ています。
新たな経験をしてみると何かしらの「気づき」があって、想像していた世界と違って見えてくるということがあるのです。
プレゼンも、ご縁があったらまずはやってみる。そこから自分が変わっていくということがあるのだと思います。
No.287 プレゼンが上達する人は「頑固」である

コンサルティングで見違えるようにプレゼンが上達する人にはある共通の特徴があります。
それは「頑固な人」です。
これって意外ですよね。
一般的には「素直じゃないと、人は伸びない」と言われています。
でも「素直」とはそもそも何でしょう。ちなみに辞書にはこう書いています。
「飾り気がなくありのままである様子」
「従順で、人の言動を逆らわずに受け入れるさま」
「非を素直に認める」「忠告を素直に聞く」「行為を素直に受ける」とよく言います。
素直さは、どうやら「受け入れる」という要素があるようです。
でもちょっと考えてみて下さい。なんでも「受け入れる」人って、どうでしょうか?
「Aにしたらいいと、思いますよ」
「そうですね。確かに。Aにします」
「それ、ダメですよ」
「そうですか。早速やめるようにします」
(なんだか物足りない)という気がしませんか。
確かに素直です。でも他人の意見を右から左に受け入れ続ける「自分がない人」のようにも見えますよね。
こんな状況を、精神科医の土居健郎はこう表現しています。
「『自分がない』とは、『私は自分というものを持っていない』、『彼は自分というものを持っていない』など、自身の内面を反省的にとらえている自己意識のこと」
よく会議で「彼には、自分の意見がない」「彼は何をやりたいのか分からない」と言われる人がいます。
こんな人も「自分がない」状態に陥っています。
組織の中で「自分がある」状態にするには、勇気が必要です。
他人と対立したくない場合は尚更です。自分の意見を強く主張すると「あいつはKY」とか「あいつは頑固」と言われてしまいますよね。
人は様々な経験を蓄積しています。だから自分なりの持論や前提を持っています。
こう考えると、人は本来「頑固」なものなのです。
この頑固さが、その人の価値観を形作っています。
一方でこの頑固さという価値観は、何か大きな壁に直面して、価値観の限界に突き当たることがあります。
こんな時には、価値観そのものを大きく変えて行く必要もあります。
その時にこそ必要なのが「素直さ」です。
こう考えると人が成長するためには、頑固さを持ちつつ、相反する素直さも持ち続けることが、必要なのです。
最初の話しに戻りましょう。
コンサルティングで見違えるようにプレゼンが上達する人は、アドバイスを受け入れつつ、自分の意見を人前で通す頑固さを持つ人なのです。
No.286 新しいことをすると成長する理由

「いままでずっとこのやり方でやってきた。だからこれでいいんだ」と言って、プレゼンのやり方を変えない人が多くおられます。
確かに、経験から確立したノウハウは安心感があります。でも、同じやり方ばかりでは成長が停滞してしまいます。
なぜなら、人の脳は新しいものを好む性質があるからです。脳科学者の茂木健一郎氏は「人の脳は100歳まで進化することができる」と言います。これが「オープンエンド」といわれるもので、脳は永遠に完成することがない構造になっているということです。
脳が進化するためには単純な条件があります。「新しいことをする」ことです。新しいことを好む脳に新しいことを提供し、新しいことを達成すれば、脳から「ドーパミン」という報酬物質が出ます。このドーパミンが脳の進化を促進するカギになるのです。
しかも、その「新しいこと」は結果が予測しにくい「不確実」なものほど良いのです。
2003年、ケンブリッジ大学のシュルツらのグループにより、不確実性とドーパミンの関係を調べた実験があります。猿に、スクリーンで様々な刺激を見せて、それぞれの刺激によって異なる確率でジュースがもらえるようにしたのです。刺激と確率は、
① 刺激Aが出ると100%確実にジュースがもらえる。
② 刺激Bが出ると50%の確率でジュースがもらえる。
としました。この実験でドーパミン細胞の活動を調べると、②50%の確率条件のほうが、刺激を見てから報酬がもらえるまで継続的な活動が続いたのです。
つまり、ジュースが確実にもらえると分かれば猿は安心し、ドーパミンの活動は下がります。一方、「ジュースがもらえるか、もらえないか分からない」という方が、より興奮して猿のドーパミンは活動的になったのです。
不確実なことにチャレンジするということは、そこから新しいことを学べるということです。特に経験を重ねた人は、体験や知識が多く蓄積されていて、「これをするとどうせ失敗する」「どうせ大したことはない」と決めつけてしまう傾向にあります。
ではどうすればよいでしょうか?
やり方をすぐに変えようとすると抵抗感があるかもしれません。まずは簡単にできることから始めると良いでしょう。
例えば、いつも演壇で話している人は、演壇から出て全身を見せて歩き回りながら話してみる。
いつもプレゼン資料を読み上げながら話している人は、内容を覚えて話してみる。
いつも質疑応答の時間をとらない人は質疑応答を行い、聴き手とコミュニケーションをとってみる。
知らないことや、気が進まないことでも、まずは行動してみることです。もしピンとこなければやめればよいのです。でも、行動してみれば意外に新しい発見があったりするものです。脳はもともと新しいものが好きですので、それをきっかけに新たな可能性が広がるかもしれません。